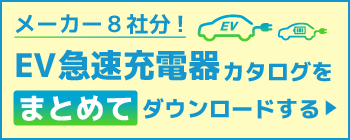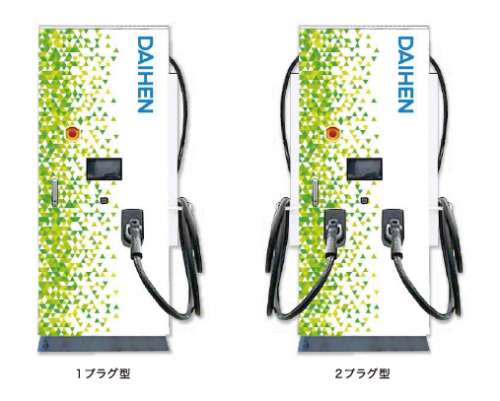日本での電気自動車(EV)の普及率は?今後の動向予測もあわせて解説
更新日:2025.04.21
近年、世界規模で注目が高まっているのが「電気自動車(EV)」です。日本でも販売台数が増加しているため、一度は見たことがある方もいるのではないでしょうか。電気自動車(EV)の普及は消費者や生産者だけの話題でなく、「急速充電器」などを設置することで、店舗や施設などの集客や顧客満足度向上も図れます。
そこでこの記事では、今後、自動車産業の中心になる可能性がある電気自動車(EV)の基礎知識と現状・課題、普及拡大に必要なインフラについて解説します。
電気自動車(EV)とは?

電気自動車(EV)とは電気を動力源として走る乗用車のことを指します。日本ではEVと称されることも多いですが、本来の「EV(Electric Vehicle)」は電気で動く乗り物の総称であり、広義の意味ではバスなども含まれることを覚えておきましょう。電気自動車(EV)は、現在自動車産業の中心である「ガソリン自動車」に代わる存在として期待されています。そのため、まずはガソリン自動車との違いを把握することが、電気自動車(EV)の理解を深めるためには大切です。
◆電気自動車(EV)の種類別の違い
| 電気自動車 | ガソリン自動車 | |
|---|---|---|
| 利用する燃料 | 電気 | ガソリン |
| 動力に変換する仕組み | モータ | エンジン |
| 二酸化炭素 | なし | あり |
| 航続距離(比較) | 短い | 長い |
| 税金(比較) | 安い | 高い |
| 補給場所 | 充電器、充電ステーション | ガソリンスタンド |
電気自動車(EV)の種類と特徴
電気自動車(EV)以外に電気を動力源として利用する自動車の種類として、HV(ハイブリッド自動車)、PHV・PHEV(プラグイン・ハイブリッド自動車)車が挙げられます。それぞれ「エネルギー」と「エネルギーを動力に変換する仕組み」が異なります。
■電気自動車(EV)の種類別の違い
| 電気自動車(EV) | ハイブリッド自動車(HV) | プラグイン・ハイブリッド自動車 (PHEV) |
|
|---|---|---|---|
| 利用する燃料 | 電気 | 電気とガソリンの併用 ※メインはガソリン |
電気とガソリンの併用 ※メインは電気 |
| 動力に変換する仕組み | モータ | モータとエンジン | モータとエンジン |
| 二酸化炭素 | なし | あり ※ガソリン車より少ない |
あり ※ガソリン車より少ない |
| 航続距離(比較) | 短い | 長い | 長い |
| 税金(比較) | 安い | ガソリン車より安い | ガソリン車より安い |
| 補給場所 | 充電器、充電ステーション | ガソリンスタンド | ガソリンスタンド、充電器 |
ハイブリッド自動車(HV)は、モータを搭載したガソリン自動車という位置付けであり、電気自動車(EV)のようにエンジンで発電することはありません。走行中に余った力を利用して発電し、コツコツとためた上で「発進・低速時」にEV走行するなどの仕組みが電気自動車(EV)と大きく異なるポイントです。また、あくまでガソリンが主な燃料のため、電気自動車(EV)のように充電器や充電ステーションは利用できません。 プラグイン・ハイブリッド自動車(PHEV)は、ハイブリッド自動車(HV)と同様にガソリンと電気の両方をエネルギーとして利用します。ただ、電気をメインの燃料として、ガソリンは補助的な利用にとどまります。また、電気自動車(EV)と同じように外部からバッテリーを充電できるのも特徴です。
電気自動車(EV)のメリット・デメリット
電気自動車(EV)は他の種類の車と比べると、メリット・デメリットの両方があります。メリットを生かし、デメリットを改善することが電気自動車(EV)の普及の鍵を握るでしょう。
社会的なメリット:環境に優しい
社会的なメリットとしてまず挙げられるのが、電気自動車(EV)はガソリン自動車と比べると環境に優しい自動車ということです。二酸化炭素の排出がゼロのため、地球温暖化などの対策として有効であり、エコな車として注目が集まっています。

消費者のメリット:乗り心地が快適でランニングコストが優れている
電気自動車(EV)は、バッテリーとモータのみで走行できるためガソリン自動車のように走行時の音や振動がほとんど発生しません。加速もスムーズで走行音も静かなので、車内でより快適に過ごしやすくなるでしょう。また、燃料費も電気代のみでガソリン代よりも安くなりやすく、補助金や減税が適用されるのでイニシャルコストの削減も図れます。

電気自動車(EV)のデメリット
電気自動車(EV)のデメリットには家庭での充電の時間がフル充電だと7~15時間かかるうえ、放電により車に乗らなくても残量が減少することが挙げられます。また、充電ステーションの数もガソリンスタンドと比べると非常に少ないので、利便性においてはガソリン自動車の方が優れているといえるでしょう。さらに補助金があるとはいえ車両価格がガソリン自動車と比べると高めであることも、デメリットの1つです。

海外での電気自動車(EV)の普及動向

IEA(国際エネルギー機関)の発表によると、2023年の世界全体の電気自動車(EV)普及率は18%で、2020年の4.2%から大幅に伸びました。また2024年の第一四半期に販売された電気自動車(EV)は300万台以上で、前年の同じ期間と比べて25%程度増加しています(※1)。
主要国・エリアの電動化目標と2023年の販売シェア率は、以下の通りです(※2)。
| 主要国 | ガソリン車 | EV・PHEV・FCV | 市場規模 | 世界販売シェア率(2023年)(※2) |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | 2030年販売禁止 ※HV/PHEVは2035年販売禁止 |
2030年販売目標 EV:50~70% |
270万台 | 24.0% |
| フランス | 2040年販売禁止 | 2028年ストック台数目標 EV:300万台 PHEV:180万台 |
280万台 | 25.0% |
| 中国 | 2035年販売禁止(※3) | 2025年販売目標 EV・PHEV・FCV:20% |
2,580万台 | 38.0% |
| ドイツ | 国の目標はなし | 2030年ストック台数目標 EV:1,500万台 |
400万台 | 24.0% |
| EU | 2035年販売禁止 ※合成燃料「e-fuel」を使用するエンジン車の販売は認める(※4) |
2035年販売目標 EV・FCV:100% |
1,400万台 | 22.0% |
| 米国 | 国の目標はなし ※カリフォルニア州知事 :2035年EV・FCV100% ※ニューヨーク州知事 :2035年EV/FCV100% |
2030年販売目標 EV・PHEV・FCV:50% |
1,750万台 | 9.5% |
電気自動車(EV)の普及をけん引しているのは、中国とEU諸国です。
中国の2020年の電気自動車(EV)販売シェア率はわずか5.7%でしたが、2023年には38.0%となっており、急速に普及が拡大しています。2023年には、バッテリーの電気のみで走行するBEVの販売台数が540万台に達しており、今後もさらなる普及が予想されるでしょう(※2)。
EU全体の2023年のEV普及率は22%でした。EUの中でも特に電気自動車(EV)の販売シェア率が高いのはノルウェーで、2023年は93.0%でした(※2)。次いで、アイスランドが71%、スウェーデンが60%となっています(※2)。その他のEU諸国も、世界の電気自動車(EV)の販売シェア率の上位に位置しています。ガソリン車販売禁止目標を掲げている国も多いため、今後はさらに電気自動車(EV)が増加していくと考えられるでしょう。
なお、EU全体として2035年以降、PHEV・HV含む内燃機関車(エンジン車)の実質廃止を掲げていましたが、現在は環境に配慮した合成燃料を使用した内燃機関車の販売は、2035年以降も認められることとなっています(※6)。
中国に次いで、世界2位の自動車販売台数を誇るアメリカですが、2023年の電気自動車(EV)販売シェア率は9.5%にとどまりました(※2) (※7)。テスラを中心に電気自動車(EV)の車種が増加傾向にあり、日本に比べると普及が進んでいますが、欧州や中国に比べるとそれほど高い販売シェア率とはいえません。ただし、2022年にアメリカの大手総合情報サービス会社、ブルームバーグが公表した情報によると、2030年までに販売される自動車のうち、52%が電気自動車(EV)になるとの予測も立てられています(※8)。
※1 出典:iea「Electric Vehicles」 https://www.iea.org/energy-system/transport/electric-vehicles
※2 出典:iea「Global EV Data Explorer」 https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer
※3 出典:朝日新聞「中国、ガソリン車を2035年に全廃へ すべて環境車に」 https://www.asahi.com/articles/ASNBW75L8NBWULFA034.html
※4 出典:朝日新聞「EU、エンジン車の販売2035年以降も容認へ 全面禁止の方針転換」 https://www.asahi.com/articles/ASR3T7DZCR3TULFA00C.html
※5 出典:経済産業省「参考資料」 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mobility_kozo_henka/pdf/004_03_00.pdf
※6 出典:讀賣新聞オンライン「エンジン車の販売、EUが35年以降も条件付きで認める…ドイツが最終段階で規制反対に転じ」 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230329-OYT1T50001/
※7 出典:GLOBAL NOTE「世界の自動車販売台数 国別ランキング・推移」 https://www.globalnote.jp/post-11249.html
※8 出典:JETRO「米国のEVシェアは2030年までに50%超と予測、インフレ削減法の効果に期待、米メディア報告書」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/09/5c0986fa2a9a53ff.html
日本の電気自動車(EV)の普及率は拡大傾向
世界全体で見ると、まだまだ電気自動車(EV)の普及率は低いですが、近年は拡大傾向にあります。
日本自動車販売協会連合会によると、国内の電気自動車(EV)の登録台数と乗用車全体での割合の推移は、以下のようになっています(※1)。
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 登録台数 | 21,139台 | 31,592台 | 43,991台 | 34,057台 |
| 全体での割合 | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.4% |
このように少しずつですが、電気自動車(EV)は普及しており、今後も拡大していくことが予想されるでしょう。また上記の数値はEV軽自動車を含めていません。日産や三菱、ホンダなどからEV軽自動車も登場しているため、実際は上記よりも普及が進んでいると考えられます。
世界全体で見ても、日本の電気自動車(EV)販売シェア率は拡大中です。2020年の日本の電気自動車(EV)販売シェア率は、世界全体のわずか0.8%でしたが、2023年には3.6%となりました(※2)。
※1 出典:一般社団法人 日本自動車販売協会連合会「年別統計(2020年~2024年)」https://www.jada.or.jp/files/libs/5110/202501081038112540.pdf
※2 出典:iea「Global EV Data Explorer」https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer
日本の電気自動車(EV)の今後
日本の電気自動車(EV)の普及率は増加傾向にあるものの、世界の電気自動車(EV)市場をけん引する中国やEU諸国と比べると、かなり差がある状況です。
しかし日本でも、政府が2035年までに、乗用車の新車販売における電動車(EV・PHEV・FCV・HV)シェア率を100%にする目標を掲げています(※1)。これに先駆ける形で、政府は2030年までに自動車の電動化目標を以下のように定めました(※2)。
- EV・PHV:20~30%
- FCV:~3%
- HEV:30~40%
また政府の目標に追従する形で、東京都は、2030年までにガソリン車の販売をゼロにする指針を示しました(※3)。
さらに政府は、2030年までに充電インフラ30万基(公共用急速充電器3万基を含む)を設置し、電気自動車(EV)の利便性を高めることを目標としています(※4)。充電インフラ拡充に向けて、法人などの団体に対し、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付も行っています。
充電インフラ拡大を目的とした補助金の詳細に関しては、こちらのページをご確認ください。
また各自動車メーカーも電気自動車(EV)の普及に積極的です。例えばトヨタ自動車は、2026年までに電気自動車(EV)10モデルを新たに市場に投入し、年間販売台数150万台を目指す計画を発表している他、2030年までに約5兆円を電気自動車(EV)に投資することを表明しています(※5)(※6)。国内の電気自動車(EV)のパイオニアである日産自動車は、2026年までに2兆円の電動化への投資を行い、2030年までに電気自動車(EV)19車種を含む電動車27モデルを投入することを計画するなど、電気自動車(EV)推進に積極的な姿勢を見せています(※7)。
今後、充電インフラが充実し、電気自動車(EV)の選択肢が増えれば、国内でも電気自動車(EV)の急速な普及が見込まれるでしょう。
※1 出典:経済産業省「自動車・蓄電池産業」 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/05_jidosha.html
※2 出典:経済産業省「自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について」 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/014_04_00.pdf
※3 出典:日本経済新聞「東京都、30年までに新車販売すべて電動車に 知事が目標」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB084YC0Y0A201C2000000/
※4 出典:経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」 https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003-1.pdf
※5 出典:EVsmartBlog by ENECHANGE「トヨタが新体制方針説明会を開催~2026年までにEV年間150万台販売へ」 https://blog.evsmart.net/toyota/toyota2026/
※6 出典:日本経済新聞「トヨタ、EV投資5兆円 「160兆円競争」の世界追う」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD02AXA0S3A500C2000000/
※7 出典:NISSAN MOTOR CORPORATION「Nissan Ambition 2030」 https://www.nissan-global.com/JP/COMPANY/PLAN/AMBITION2030/
脱ガソリン自動車が広がる背景
日本を含めた世界中で急速に脱ガソリン自動車が広がる背景には、「脱炭素社会(カーボンニュートラル)」が大きく関わっています。脱炭素社会とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引き、「実質ゼロ」になった社会を指します。
「2050年カーボンニュートラル」という120ヵ国以上が取り組む世界共通の目標を実現するためには、二酸化炭素を排出するガソリン自動車を脱却し、環境に優しい電気自動車(EV)の普及を拡大しなければなりません。
日本も2020年10月、カーボンニュートラルを目指すことを政府が宣言しました。また、自動車産業のカーボンニュートラル実現に向けた経済対策も打ち出しています。
■経済対策パッケージ
| 目的 | 予算 |
|---|---|
| 蓄電池の国内製造基盤確保 | 2021年度補正予算:1,000億円 2022年度当初予算:15億円 |
| 電気自動車、燃料電池自動車等の購入補助 | 2021年度補正予算:250億円 2022年度当初予算:140億円 |
| サプライヤー、販売・整備業の構造転換支援 | 2021年度補正予算:125億円 2022年度当初予算:90億円 |
| 充電、水素インフラの整備 | 2022年度当初予算:4億円 |
※出典:経済産業省「第4回 モビリティの構造変化と2030年以降に向けた自動車政策の方向性に関する検討会 参考資料」
政府はこれらの予算を投じ、2030年の自動車の電動化の目標(EV・PHV:20~30%、FCV:~3%、HEV:30~40%)の達成を目指す方針です(※)。
※出典:経済産業省「自動車分野のカーボンニュートラルに向けた国内外の動向等について」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/014_04_00.pdf
日本国内における電気自動車(EV)普及の課題
政府や各自動車メーカーが電気自動車(EV)の普及に力を入れています。しかし前述した通り、2023年の日本の電気自動車(EV)販売シェア率は3.6%で、諸外国と比べると、まだまだ十分に普及しているとはいえません(※)。
国内における電気自動車(EV)普及の課題の一つとなっているのが、充電インフラの不足です。また、ガソリン車に比べて電気自動車の車両本体価格が高いことも、電気自動車(EV)の普及を停滞させている要因の一つとなっています。加えて、ガソリン車に比べると電気自動車(EV)の航続距離が短い傾向にあることも、消費者が電気自動車(EV)購入に踏み切れない要因になっているといえるでしょう。
※出典:iea「Global EV Data Explorer」https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/global-ev-data-explorer
充電ステーションなどのインフラ

2023年の日本の充電インフラ設置台数は4.0万台で、2022年から2023年で25%も設置が拡大しています(※1)。しかし諸外国と比較すると、まだまだ十分な充電インフラが確保されているとはいえません。各国の充電インフラの設置状況は以下の通りです(※2)。
| 日本 | アメリカ | ドイツ | イギリス | フランス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 充電インフラ設置台数 (2023年) |
4.0万基 (うち急速充電器:1.0万基) |
18.3万基 (うち急速充電器:4.3万基) |
10.8万基 (うち急速充電器:2.1万基) |
5.3万基 (うち急速充電器:1.0万基) |
11.8万基 (うち急速充電器:2.0万基) |
さらなる電気自動車(EV)の普及を目指すためには、充電ステーションの数を増やすことが必要不可欠です。前述した充電インフラ拡大を目的とした政府の補助金政策によって、今後充電インフラが充実していくことが期待されています。
また電気自動車(EV)用充電器に関する法規制を緩和し、マンションなどの集合住宅でもEV充電設備を配備しやすくする必要もあるでしょう。
なお電気自動車(EV)用充電器には以下の3種類があり、それぞれ異なる目的を持っています。
■充電器の種類と目的
| 充電器の種類 | 目的 | 概要 |
|---|---|---|
| 普通充電器 | 基礎充電 | 通勤や買い物の小まめな充電や日常移動で活用 |
| 急速充電器 | 目的地充電 | レジャー・ドライブなどの目的地や施設で充電する |
| 大出力急速充電器 | 立ち寄り充電 | 長距離移動中の休憩場所での充電。 より早く充電が完了する必要がある |
※1 出典:経済産業省「自動車市場と充電インフラ整備の動向」https://www.chademo.com/wp2016/wp-content/japan-uploads/2024GA/METI_2024GA_ppt.pdf
※2 出典:経済産業省「自動車市場と充電インフラ整備の動向」https://www.chademo.com/wp2016/wp-content/japan-uploads/2024GA/METI_2024GA_ppt.pdf
車両本体の価格
一概にはいえませんが、前述した通り、電気自動車(EV)の車両本体価格はガソリン車と比べると高額な傾向にあります。
しかし近年は、EV普通車よりも価格が抑えられるEV軽自動車も台頭してきました。新車の電気自動車(EV)の価格帯は、コンパクトカーで360万~730万円程度、コンパクトSUVで400万~900万円程度ですが、EV軽自動車は210万~310万円程度なので、大幅に購入費用を抑えられます。ニーズに応じて車種を選択しやすくなっているため、今後電気自動車(EV)を選ぶ消費者は増えてくると予想できるでしょう。
また政府は、電気自動車(EV)を含めたクリーンエネルギー自動車(CRV)の普及を促進するために、「CEV補助金」を交付しています。CEV補助金の上限額は、以下の通りです(※)。
| 車両種別 | 基本補助額 |
|---|---|
| EV | 15万~85万円 |
| EV軽自動車 | 15万~55万円 |
| PHEV | 15万~55万円 |
| FCV | 上限255万円 |
また、2025年度からは環境負荷の削減やGX(グリーントランスフォーメーション)推進に向けた、鋼材導入に関する自動車メーカーの計画や取り組みを評価するための加算措置が導入される予定です。この評価結果に基づき、上記の基本補助額に加えて、5万円の補助金が加算されることになります。2025年度のCEV補助金の申請開始は、3月中下旬頃の予定です。
前述した通り、EV軽自動車の価格帯は210万~310万円程度ですが、補助金を活用すれば最大60万円の補助が受けられるので、ガソリン車の軽自動車とほとんど変わらない価格で電気自動車(EV)を購入できます。
※出典:経済産業省「令和7年度におけるクリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進補助⾦(CEV補助⾦)の取扱い」https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/r6CEV.pdf
走行可能距離
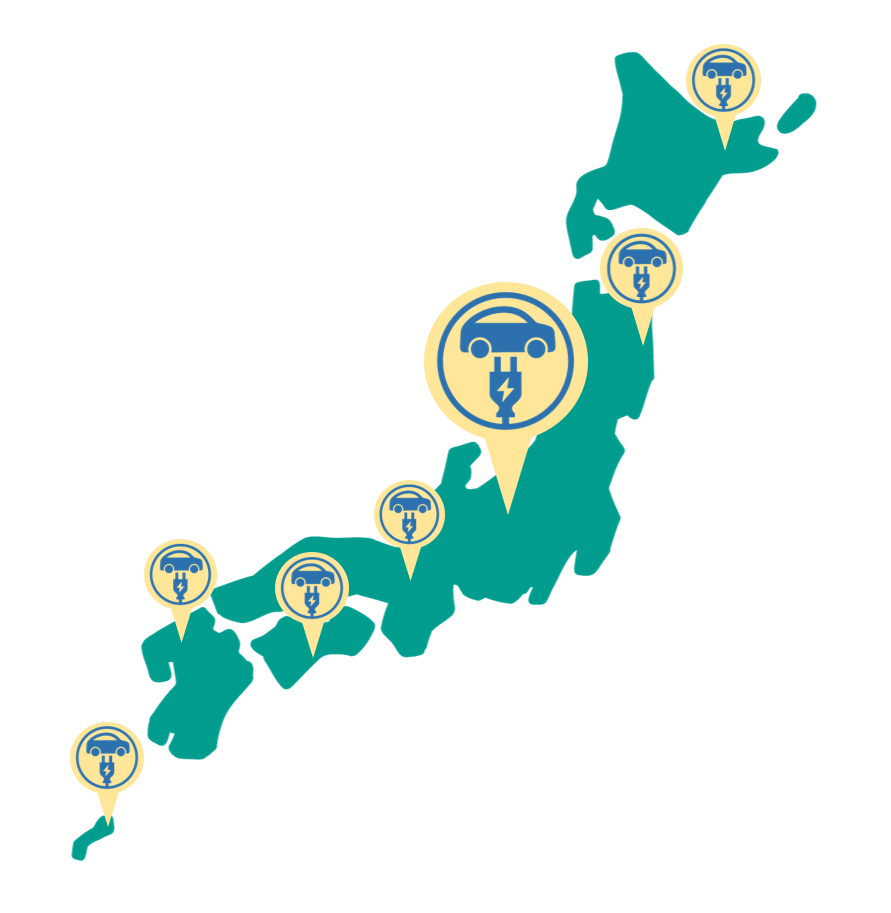
電気自動車(EV)がフル充電した場合の走行可能距離(航続距離)は200〜600kmとされています。一方、ガソリン自動車の走行可能距離は満タン給油で600〜1,500kmです。
近年は電気自動車(EV)の進化に伴い、走行可能距離が長い車種も登場しており、今後さらなる技術革新が進めば、1回の充電での走行可能距離が伸びる可能性はあります。しかし、ガソリン車ほどの走行可能距離が維持できないことに加え、まだ充電ステーションなどのインフラ整備が十分ではないことがネックとなり、現時点では電気自動車(EV)の購入に踏み切れない人も多いでしょう。
充電ステーションの設置が電気自動車(EV)の普及の鍵
日本と世界の電気自動車(EV)の普及率について解説しました。現在、国や自治体を上げてさまざまな取り組みが行われていますが、まだまだ普及が進んでいるとはいえません。
電気自動車(EV)が抱える課題の中でも、普及の成功に大きく関係してくるのが、充電ステーションなどの充電インフラの拡充です。国内の電気自動車(EV)用充電器設置数は、以下のように推移しています(※1)。
| 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通充電器 | 21,549基 | 21,810基 | 23,256基 | 30,195基 |
| 急速充電器 | 7,893基 | 8,265基 | 8,995基 | 10,128基 |
いずれも年々少しずつ増加していますが、政府が掲げる2030年までの充電器の設置台数目標・30万基にはまだまだ程遠いのが現状です(※2)。カナデンでは、国内で販売されている電気自動車(EV)の多くに対応している充電規格「CHAdeMO(チャデモ)」に対応した急速充電器をはじめ、さまざまなサイズ・出力量の電気自動車(EV)用急速充電器を取りそろえ、電気自動車の普及率の向上に貢献していきます。急速充電器の導入を検討されている方は、ぜひお気軽にカナデンへお問い合わせください。
※1 出典:経済産業省「自動車市場と充電インフラ整備の動向」https://www.chademo.com/wp2016/wp-content/japan-uploads/2024GA/METI_2024GA_ppt.pdf
※2 出典:経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003-1.pdf