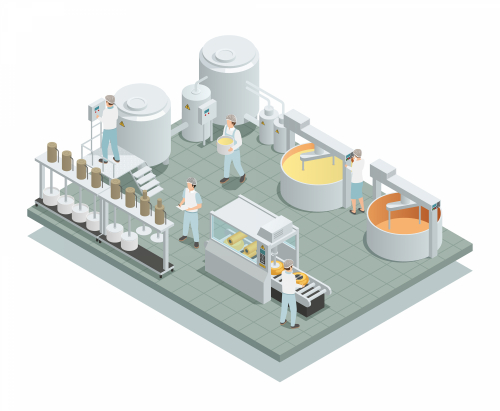PFAS規制強化の波にどう対応する?製造・工事業者が今すべきこと
2025年10月17日
製品・サービス紹介
- 製品・サービス
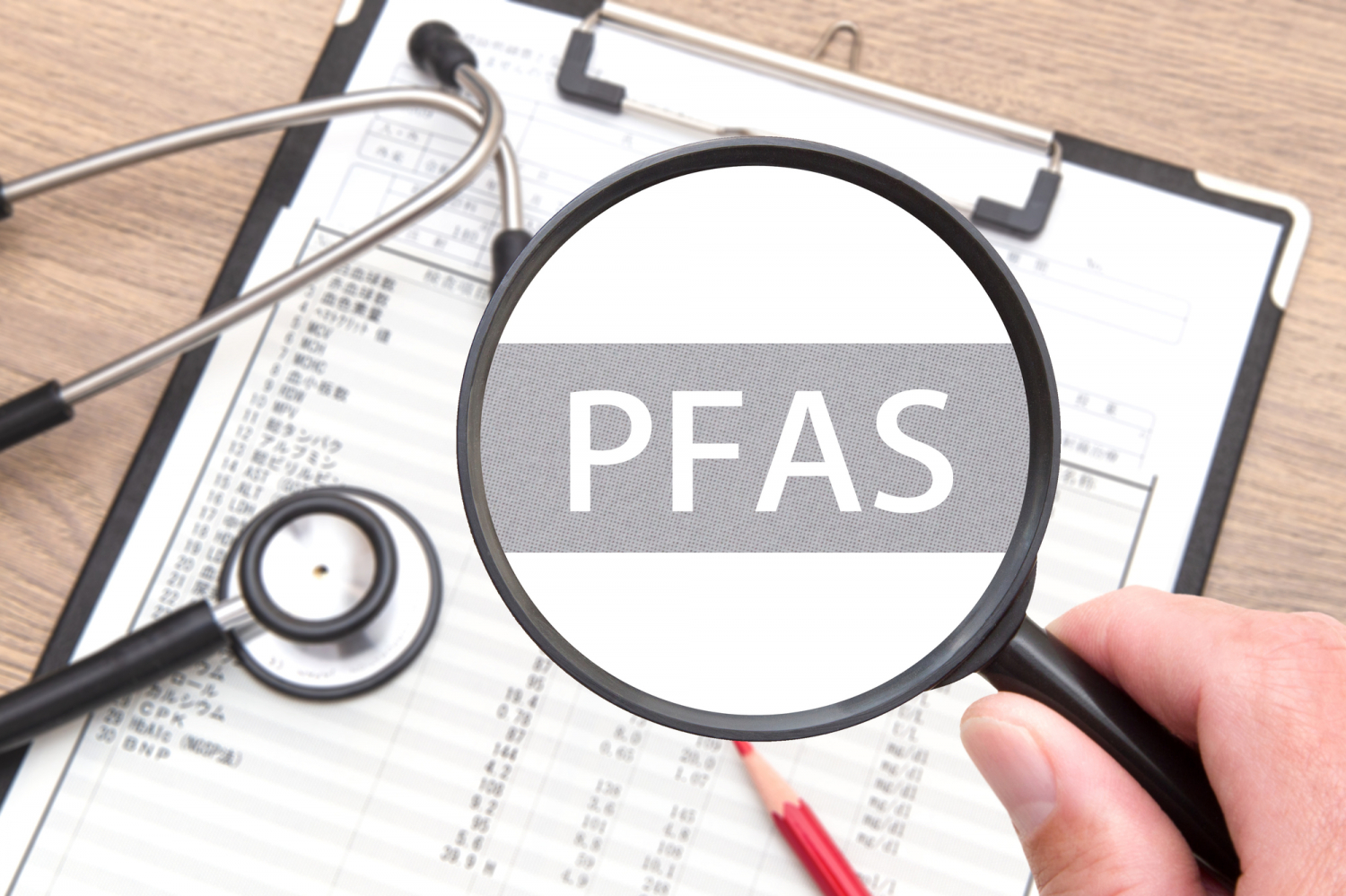
近年、PFAS(ピーファス)と呼ばれる有機フッ素化合物に対する国際的・国内的な規制が急速に強化されています。
製造業や工事業に従事されている皆様にとって、これは単なる環境問題ではなく、事業の持続可能性と信頼性にかかわる重要な課題です。
PFASは、撥水性や耐熱性などに優れているため、包装用紙、フライパンの表面加工剤、防水布地、メッキ処理剤、泡消火薬剤など、さまざま用途で広く利用されてきました。
しかし、一度環境中に放出されると自然界で分解されにくく、環境中に長期間残留し、生物の体内に蓄積しやすいという問題点が指摘されています。
本記事では、PFASの基礎知識から、特に2026年に向けて厳格化する日本の規制動向、そして企業が今すぐに取り組むべき具体的な対策までを解説いたします。
PFASとは何か?なぜ問題視されるのか
PFASとは、約1万種類が存在するとされている有機フッ素化合物の総称です。
炭素とフッ素の結合が極めて強固(きょうこ)なため、熱や化学物質に対して高い抵抗性を示し、分解されにくいという特徴を持ちます。
PFASの中でも特に知られ、規制対象となっているのが、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)です。
これらが問題視されている主な理由は以下の通りです。
有害性
動物実験の結果、肝臓機能の低下や赤子の体重減少への影響が指摘されています。
人においては、コレステロール値の上昇・発がん・免疫系などとの関連が報告されていますが、どの程度の量が人体に入ると影響が出るのかについては、確定的な知見は無いのが現状です。
長距離移動性・残留性
フッ素と炭素を人工的に結合させたものであることから、自然界で分解されにくく、環境中に長時間残留するとされています。この特徴を指して、「永遠の化学物質」と呼ばれることもあります。また、水溶性(水に溶け出す性質)もあるため、河川や海などの水系を通して広く拡散します。
日本の規制動向:2026年に向けて水質基準が厳格化

日本では、PFASの中でも特にPFOS、PFOA、そしてPFHxS(ピーエフヘキサエス)の3種類が、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき「第一種特定化学物質」に指定され、製造・輸入・使用が原則禁止されています。
・PFOS:2010年に製造・輸入・使用が原則禁止
・PFOA:2021年に製造・輸入・使用が原則禁止
・PFHxS:2023年に製造・輸入・使用が原則禁止
これらの物質は、使用が禁止されるまで、PFOSはフライパンのメッキ処理剤や泡消火薬剤などに、PFOAは上着の撥水剤や界面活性剤などに使われていました。
PFHxSはPFOSの代替物質として使われていた背景があります。
特に製造業や工事業の皆様が意識すべきは、水道水や排水に関する規制強化です。
現在、PFOSとPFOAの合計値について「50ng/L以下」という暫定目標値が定められています。
この暫定目標値は、2026年4月1日より水道水基準項目に格上げされる見通しです。
この基準値(水道水1リットルあたり、PFOSとPFOAの合算値で50ナノグラム以下)は法的拘束力を持つため、各地の水道事業者には、おおむね3ヵ月に1回以上の定期的な検査が義務づけられ、基準を超過した場合には法的に改善措置を取る必要が出てきます。
また、水質汚濁防止法においても、PFOSとPFOAが「指定物質」に追加されており、排出事故時の応急措置や行政報告が義務化されています。
今後は欧米の動向を踏まえ、対象物質の拡大や基準値の見直し、報告義務の強化などの法改正が進む見込みです。
※出典:環境省「PFAS に関する今後の対応の方向性」https://www.env.go.jp/content/000150418.pdf
※出典:環境省「「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について」https://www.env.go.jp/press/press_00075.html
世界の厳しい規制トレンド
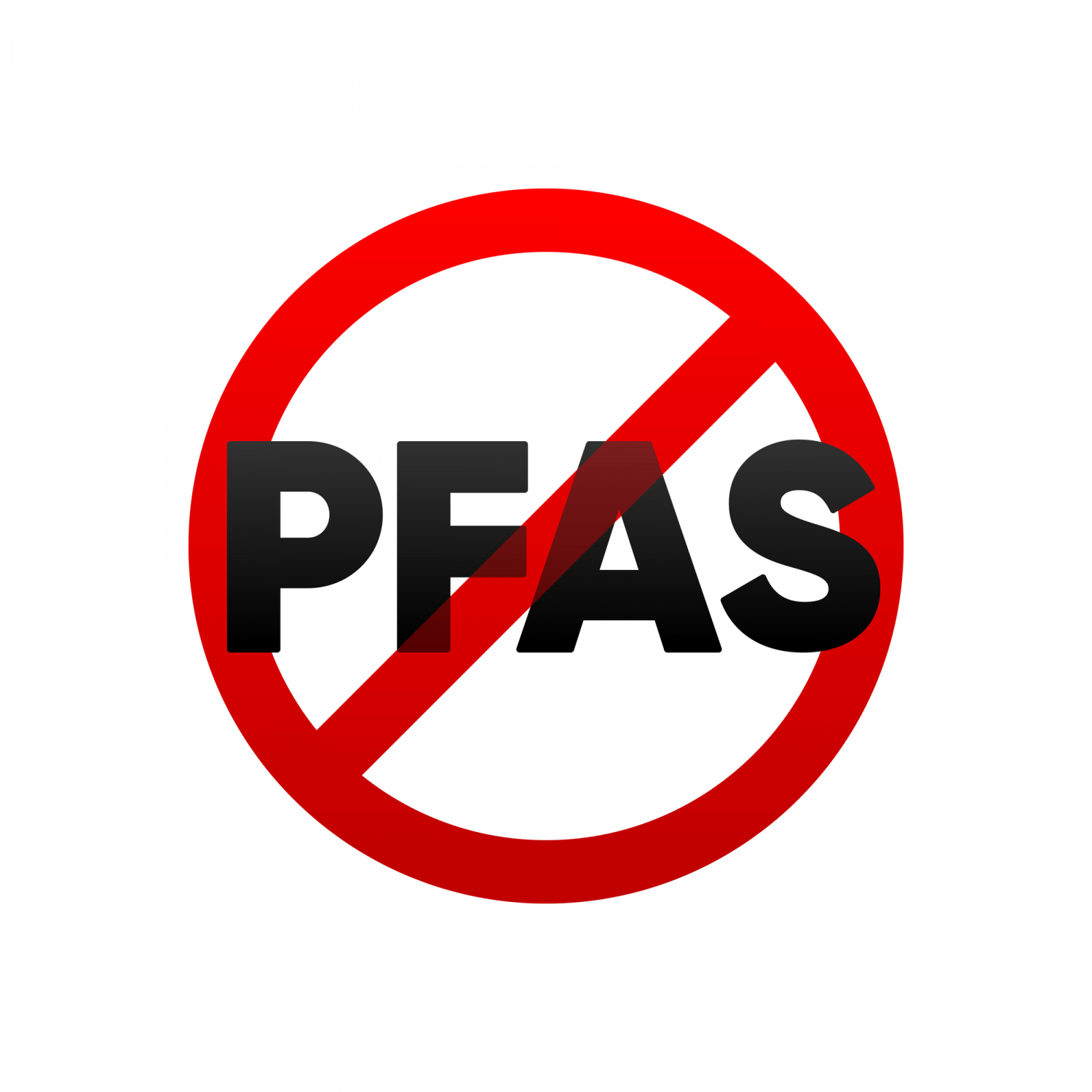
日本の規制強化は、PFASのリスクが世界的に注目され、各国で規制枠組みが急速に整備されてきたことに追随する動きです。
規制急進派の国々では、すでに非常に厳しい基準が導入されています。
アメリカ
環境保護庁(EPA)は、2024年4月にPFOS・PFOAの目標値を「4ng/L」という非常に厳しい値に設定しました。
2027年までには、全国の公共水道システムでのモニタリングも義務化される見通しです。
EU
飲料水指令により、PFASというくくりに含まれるさまざまなフッ素化合物の合計が「500ng/L」を超えてはならないという規制や、20種類の特定のPFAS類の合計値は「100ng/L」以下とする規制が定められています。
EUのREACH規則では、2023年に全PFASをまとめて制限する包括的な提案が提出されるなど、広範囲の規制へとシフトしているのが現在のトレンドです。
国際条約であるPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)でも、PFOSやPFOAの生産・使用が原則禁止とされており、最近ではPFHxSも新たに対象となっています。
国際会議の結果によって、各国のPFAS規制にさらなる影響があると予想されます。
グローバルに事業を展開する企業にとって、欧米の厳格な規制に対応するため、製品の製造や流通網を根本から見直す必要が生じています。
企業が取るべきPFAS除去対策と実務ポイント
PFAS規制が世界的に強化される中、企業や自治体では除去技術の導入が加速しています。
特に水処理分野では、吸着材を使った除去が広く活用されており、飲料水や工業排水からのPFAS対応が現実的な手段となっています。
水処理で実用化されている主なPFAS除去技術は以下の通りです。
粉末活性炭・活性炭
多孔質構造(表面に無数の小さな穴があること)を利用してPFASを物理吸着することで、効果的な除去が可能です。
高い除去力を有しますが、一定期間の使用後は焼却・地中廃棄や特別な再活性処理が必要となり、ランニングコストの面で課題を抱えています。
イオン交換樹脂
活性炭と似ており、大きな比表面積を持ちます。
PFOSやPFOAに対して良好な除去性能を有していることが実験により証明されています。
ただし、活性炭と同様、ランニングコストや処分に掛かる費用がかさむ可能性があります。
逆浸透膜(RO膜)
非常に小さな粒子だけを通す微細な孔(あな)が空いた「半透膜」を用いたろ過処理です。
高い圧力をかけることで、水の分子だけを膜の反対側に移動させる仕組みです。
工業用水の水質改善などで活用されており、純水を作り出すことが可能です。
製造業や工事業の皆様は、まず自社でのPFASの使用実態を正確に把握するための水質検査を行うことが重要です。
その上で、検査で基準値を超えるPFASが見つかった場合には、これらの除去技術を導入する等の処理方法を検討する必要があります。
まとめ:リスク管理と持続可能な経営のために
PFASは、高性能ではあるものの、環境や健康への懸念から、世界各国で規制が強化されています。
日本でも2026年4月に水道法の基準が厳格化され、企業には一層の対応が求められます。
企業は、規制対応をリスク回避にとどめず、持続可能な企業活動の一環と位置づけることが重要です。
早めの対策と体制整備で、企業の信頼を維持していきましょう。