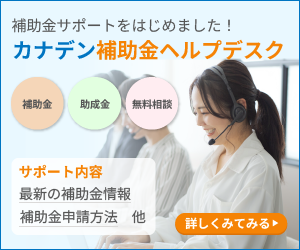【令和7年度】工作機械の導入時に使える補助金とは?補助金を使うメリットや受給までの流れを解説
公開日:2024.05.10 更新日:2025.04.30
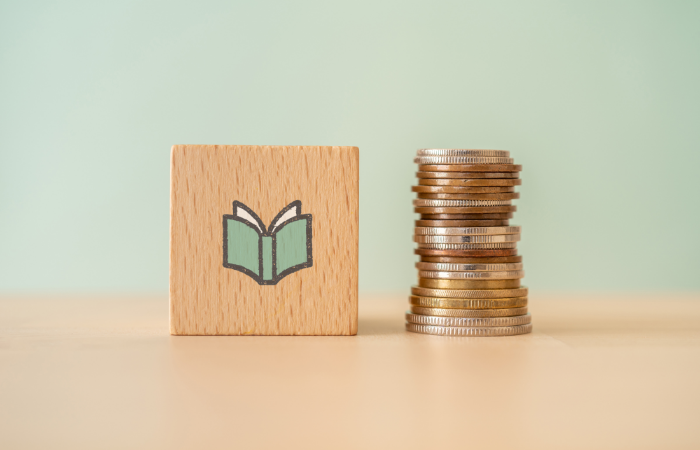
工作機械設備を導入する際は、申請して認められれば補助金を受給できます。補助金の適用範囲は幅広く、種類も多いため、自社に適した支援を受けられるというメリットがあります。
一方で「補助金を申請するだけでもかなりの手間がかかる」「申請期間が短い」などのデメリットも挙げられます。そこで本記事では補助金の基本事項やメリット・デメリット、受給の流れについて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
※2025年2月時点の情報です
工作機械の導入時に使える補助金とは
工作機械の導入時に使える補助金とは何か、助成金の違いと共に説明します。また補助金を受給する条件や経費の例についても紹介します。条件などは制度内容によって異なるので、実際に申し込む際は公式サイトなどで確認しましょう。
補助金とは
補助金とは新規事業や公益事業などの取り組みに対し、費用の一部をサポートするかたちで給付してもらえる、返済不要な資金のことです。補助金にはさまざまな種類があり、各省庁や自治体、民間団体による補助金も存在しますが、主な管轄機関は経済産業省です。給付される金額の割合や上限額は、補助金の種類によって異なります。
補助金を受けたい方は、期間中に申請をする必要があります。公募期間は短く、1カ月前後に設定している場合が多いことを留意しておきましょう。一般的に、2月から6月頃までに募集が開始されることが多いです。
また補助金は、必ずしも全ての申請者に交付されるわけではありません。補助金の交付には審査があるため、審査に通らなければ受け取れない点に注意しましょう。原則後払い(精算払い)のため、検査が通った後に受け取れるケースが多いです。
※出典:経済産業省「中小企業庁 - ミラサポPlus」https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/guide/
助成金との違い
補助金と似た用語に「助成金」があります。補助金の目的が新規事業や公益事業などの取り組みへの支援であるのに対し、助成金は労働環境の安定を目的としています。また補助金の管轄が経済産業省であるのに対し、助成金の管轄は厚生労働省です。交付される金額にも差があり、補助金は上限額が数千万円~数億円にまで広がっているのに対し、助成金の交付額の中心は数十万円〜数百万円程度です。
また補助金は審査を通過しなければなりませんが、助成金は要件さえ満たせば原則受給できるという違いがあります。公募期間に関しても、補助金は一定期間のみであるのに対し、助成金は通年公募を実施しているケースが多いです。
※出典:厚生労働省 「業務改善助成金」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
※出典:経済産業省「事業再構築補助金 第13回公募の概要 1.0版」https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/download/summary013.pdf
補助金対象者
補助金の対象者は、制度ごとに異なる条件が設定されています。ここでは、例として東京都墨田区の制度を紹介します。墨田区では、以下の条件を満たす方が補助金の対象となります。
- 中小企業者であること
- 区内に1年以上主たる事業所を有すること
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- 風俗営業などの規制や業務の適正化に関する法律に反する営業を行っていないこと
また対象となる経費は以下のとおりです。
- 工作機械や測定機器などの機械・装置の導入経費
- 上記に付帯する工具や器具の導入経費
※2025年2月時点の情報です
※出典:墨田区「【申請の受付を終了しました】工作機器等導入支援」https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/hojokin_joseikin/kikidonyu.html
カナデン補助金ヘルプデスクでは、カナデンで取り扱い可能な製品について補助金・助成金が受給できるよう、全面的にサポートいたします。
補助金に関するお問い合わせは次のヘルプデスクページよりお願いいたします。
工作機械の導入・購入時に使える補助金の種類を紹介
以下では工作機械の導入・購入時に使える補助金を4つ紹介します。各補助金を受け取るには、申請受付期間内に申請を行い、補助金の審査時に「要件を満たしている」と判断してもらう必要があります。申請受付期間は年度によって変わるため、実際に申し込む場合は、公式の募集要項を確認しましょう。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に取り組む企業のために、設備投資資金として支給される制度です。
第19次公募の公募要領は2025年2月14日(金)に公開され、申請開始は2025年4月11日(金)17時、締切日は2025年4月25日(金)17時までとなっています。
補助金の支給を受けるためには、下記の要件を満たす3〜5年の事業計画の策定と実行をする必要があります。
- 付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上または給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※2025年2月時点の情報です
※出典:全国中小企業団体中央会 「ものづくり補助金総合サイト」https://portal.monodukuri-hojo.jp/
※出典:中小企業庁 中小企業対策関連予算 「令和6年度補正予算ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金概要」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_mono_summary.pdf
中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制とは、指定期間内に新品の機械装置などの設備を取得・製作した中小企業に対して、特別償却または税額控除を認める制度のことです。これまで制度の内容は数年単位で変更されており、2025年度の税制改正では適用期限が2027年3月末までに延長される見込みです。
中小企業投資促進税制のうち、特別償却の限度額は、基準取得価額の30%です。例えば設備の取得に100万円かかった場合、初年度は30万円を特別償却として計上できます。これを普通償却限度額に加えた金額が、全体の償却限度額に当たります。
また税額控除限度額は、基準取得価額の7%です。上限も設けられており、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」で受ける税額控除とこの制度で受ける税額控除の合計が、事業年度の調整前法人税額の20%までとなるよう定められています。
なお税額控除が選べるのは資本金3,000万円以下の法人・個人事業主のみです。資本金が3,000万円を超えている場合は、特別償却のみ選択できます。
※2025年2月時点の情報です
※出典:国税庁「中小企業投資促進税制」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
※出典:経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者に対し、自社の持続的な経営の向上を図るための経営計画作成や、販路開拓など生産性向上の取り組みを支援するための補助金です。
2024年の申請は5月27日に締め切られ、2024年8月8 日に採択結果が出ました。2025年2月現在、今後の公募予定は発表されていません。しかし、令和6年度補正予算事業の概要が示されていることから、2025年度も公募が実施される見込みです。また、政策の原点回帰に伴い、経営計画の策定が重視される方針となっており、複数の特別枠が整理される見通しです。
令和6年度補正予算事業の補助率は2/3、上限額は一般型でインボイス特例と賃金引上げ特例を活用した場合、最大250万円です。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は、補助率が3/4に変わります。
※2025年2月時点の情報です
※出典:全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(一般型)」https://s23.jizokukahojokin.info/
※出典:中小企業庁 中小企業対策関連予算「持続化補助金の概要」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_jizoku_summary.pdf
事業承継・M&A補助金
2024年度までは「事業承継・引継ぎ補助金」として実施されていましたが、令和6年度補正予算では「事業承継・M&A補助金」へと名称が変更されます。本補助金は、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資やM&A時の専門家活用、M&A後の経営統合(PMI)、事業承継・M&Aに伴う廃業などにかかる費用を補助する制度です。「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4類型があります。
2025年2月現在、今後の公募予定は未発表ですが、2025年3月3日を締切として、令和6年度補正予算に基づく「事業承継・M&A事業」にかかる事務局公募が行われています。事務局の決定後、すぐに公募が行われる場合でも、準備期間を考慮すると、公募開始は3月中旬から4月頃になる見込みです。
※2025年2月時点の情報です
この補助金は中小企業や小規模事業者が申請対象ですが、要件さえ満たせば個人事業主も補助金を受け取れます。
※出典:中小企業庁 中小企業対策関連予算「事業承継・M&A補助金」https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
※出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「令和6年度補正予算「事業承継・M&A事業」に係る事務局の公募について」https://www.smrj.go.jp/procurement/solicitation/f7mbjf0000001dik.html
工作機械 関連製品一覧工作機械の補助金を使うデメリット

工作機械の補助金は、申請すればすぐに支給されるわけではありません。さらには各種補助金にはメリットばかりでなくデメリットもあります。ここでは、工作機械の補助金を使うことに対するデメリットを解説します。
申請まで時間がかかる
工作機械の補助金を使う際は、申請の段階で手間や時間がかかることがデメリットとして挙げられます。補助金申請時には、特別に提出を求められる書類が多いからです。手順が複雑化しているケースもあり、申請自体を難しいと感じる方もいるでしょう。
特に申請時の提出書類として作成に手間がかかるのが「事業計画書」です。事業計画書は自社がいかに補助金を必要としているかを伝える書類なので、図や写真・グラフなどを活用し、視覚的に分かりやすい資料となるよう工夫する必要があります。また計画の内容にもこだわり、導入する設備や数値計画の根拠といった詳細な内容を、しっかりと記載することが求められます。
事業開始前に受給できない
補助金は前払い制ではありません。したがって事業開始前には受給できない点に注意しましょう。補助金を受け取るには、申請時に提出した事業計画書どおりに事業を行い、終了後に実施内容を報告します。かかった費用×補助率を算出し、清算払いの請求を行うのが一般的な流れです。
清算払いの請求は、事業の確定検査を受けた上で、補助金額が確定しなければ行えません。せっかく時間や手間をかけて事業計画書を作成しても、実際に事業を計画通り行えなければ、補助金が認められない可能性もあるのです。
こういった理由から、補助金は「すぐにでも費用を支援してほしい」と考えている事業には向いていないといえるので、注意しましょう。
募集期間が短い
補助金は申請期間が限られていることもデメリットの一つです。申請時に必要な書類の準備や作成に手間がかかるにもかかわらず、公募期間は短い場合が多いので、スケジュールを逆算して準備しておく必要があります。
例えば先述した「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第19次公募の申請期間は、2025年4月11日(金)17時から4月25日(金)17時までの約半月と、短く設定されています。申請開始前に公募要領が公開されているものの、限られた時間内で各種書類を準備する必要があり、申請者にとって大きな負担となります。
補助金の採択率が低い
補助金を申請しても、採択率は決して高くないのが現状です。採択率は制度や年度によって異なりますが、全体のおよそ30〜60%とされています。
先ほど例に挙げたものづくり補助金(18次締切における申請者数、採択者数より)の場合は、2024年3月27日から2024年6月25日までの期間に5,777名の申請者がおり、そのうち採択されたのは2,070名でした。申請者のうち、約半数以上が不採択となったことが分かります。
不採択になれば、申請に要した手間や時間が無駄になってしまうかもしれません。
補助金の申請が通る確率を高めるには、事業計画の策定や事業計画書類の作成を慎重に行う必要があります。自社で行うには負担が大き過ぎる場合は、補助金の申請支援を行っているプロに相談するのも一つの手です。
カナデン補助金ヘルプデスクでは、補助金申請に関する相談を無料でお受けしています。また補助金ごとに異なる要件や申請時期、法改正などについての最新情報をお届けし、補助金を受けたいとお考えの企業のご担当者様をサポートいたします。補助金申請でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※出典:全国中小企業団体中央会「採択結果」https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html
補助金対象製品一覧工作機械の補助金を使うメリット
工作機械の補助金には申請の手間などの負担がある一方、メリットも大いにあります。ここからは、補助金の4つのメリットについて詳しく紹介します。補助金を申請する際はメリットとデメリットを比較し、自社にとってメリットの方が上回る方法を検討しましょう。
事業計画を改めて考えられる
応募申請書や事業計画書などの書類の準備は、手間と時間がかかる一方、自社の事業に対して改めて考え直すきっかけになります。補助金の申請をきっかけに、これまでの事業について今一度”棚卸し”することで、人材育成や設備投資など自社に必要な新たな取り組みが見えてくることもあるかもしれません。
対象経費の範囲が広い
補助金には、対象となる経費の範囲が広いというメリットがあります。そもそも補助金は、国や地方公共団体における経済の発展と活性化を促進する目的で資金を支給する制度なので、目的達成のためには広い範囲で民間の企業を対象とする必要があるのです。
また補助金は助成金よりも種類が多いため、自社の状況に合う制度を見つけやすいメリットもあります。例えば従業員がおらず「社長一人のみ」「役員のみ」という会社でも、補助金の種類によっては申請できることもあります。
返済しなくてもよい
補助金制度で支給されたお金は、基本的に返済不要です。例えば新規事業を始めるに当たり資金を確保したい際などは、金融機関から融資を受けるという方法もありますが、融資の場合は最終的には金利を含めて返済する必要があります。事業用ローンは5年〜7年という短期間で返済しなければならないため、経営状況によっては大きな負担となる可能性もあります。
補助金であれば支給されるのは費用の一部ではあるものの、原則として返済の必要がありません。この点は、大きなメリットといえるでしょう。
事業の価値が向上する
補助金の申請が通れば、自社の事業の価値向上につながります。なぜなら補助金は厳しい審査を通過した企業だけに支給されるため、採択された時点で「申請企業の事業計画に経済的発展性と将来性がある」と認められたことになるからです。
また補助金の支給を受けるためには、社会貢献性が高い事業であることも求められます。自社の事業を社会貢献性の高いものにブラッシュアップできることも大きなメリットです。
さらには補助金の申請が通ったという事実が、申請企業の社会的信頼度を上げることにもつながります。そうすれば事業の価値も高まり、やがて収益向上につながっていくでしょう。
補助金を受給するまでの流れ

次に、補助金を受給するまでの流れを紹介します。工程ごとに必要なものや行うこと、補助金受給までの期間などを説明します。
自社に合う補助金制度を検索する
まずは自社にマッチする補助金制度を、時間をかけて調べることが大切です。くり返しになりますが、補助金にはさまざまな種類があり、目的も要件もそれぞれ異なります。数ある補助金の中から気になる補助金を探してみてください。
検討するポイントとしては、自社の機械設備の購入・導入が対象となっているかを確認しましょう。補助金の対象や内容は毎年変わる可能性があります。たとえ過去に同様の補助金を受給した経験があったとしても、その内容と同じとは限らないため、最新の内容を必ずチェックしてください。
「カナデン補助金検索システム」では、補助金に関する最新情報と共に、条件に適した補助金を検索できます。自社に合う補助金制度をお探しの際は、ぜひご利用ください。
申請書を作成する
自社にマッチした補助金が見つかったら、次は申請に向けて書類作成に入ります。申請書の作成にはまとまった時間を要するため、スケジュールをしっかり立てた上で取り組むことが大切です。
申請書では、自社の新たな取り組みが、いかに有意義なものであるかを示す必要があります。そのため自社が取り組む事業や見通しなどを、網羅的に可視化することが大切です。事業内容によっては、A4サイズの用紙に何枚も記載する可能性もあります。相手にとって読みやすいように、字数制限を守る、専門用語には注釈を付けるといった気遣いをするのも良いでしょう。
自社の力のみで申請書を完成させるのが難しい場合は、専門家のサポートを受けるのもおすすめです。
申請する
必要書類の準備ができたら、修正すべき点がないかを確認してから提出します。補助金の種類によって異なりますが、必要書類の例としては「応募申請書」「事業計画書」「経費明細書」「事業要請書」などが挙げられます。抜け漏れがないかしっかりチェックしましょう。
必要書類の提出方法も補助金によって異なるため、事前に公式サイトなどで確認してから提出します。紙の書類を提出する方法以外に、電子申請を採用しているところもあります。電子申請では事前登録が必要なケースがあるため、できるだけ早めに対応しましょう。
1~2カ月ほどで採択される
申請後は審査に入るため、採択を待ちます。通常、審査には1〜2カ月ほどかかることがほとんどです。また申請書類に記載の内容だけでは判断がつかなかったり、審査に当たって他に確認事項があったりするケースも考えられます。その場合は書類審査だけでなく「ヒアリング」も行う、二段階審査になることがあります。いずれにせよ、結果が出るまでは数カ月かかると見越して、余裕のあるスケジュールを立てましょう。
採択されたら、補助金を受け取るための手続きである「交付申請」を行います。
事業をスタート
審査により必要書類および事業計画の妥当性が認められれば、交付決定の採択が下り、補助事業を開始できます。先述のとおり、補助金を受け取りたい場合は交付決定までの期間中は申請事業に着手できません。
ただし採択が下りたからといって、事業は必ずしも計画書どおり行くとは限らず、スケジュールがずれ込むこともあります。したがって採択後は即座に取り掛かれるよう準備をしておくことが大切です。また実際に事業に取り組んでみると、内容を変更せざるを得ない場面が出てくるかもしれません。その場合は、所定の手続きに沿って、速やかに変更を報告しましょう。
なお領収書や証拠書類は事業の完了報告に必要となるため、忘れずに保管しておいてください。
事業の完了報告・受給
補助事業が完了したら、「どのような内容で行ったのか」「経費はいくらかかったのか」などの報告書を提出し、完了報告を行います。報告書の内容と照らし合わせて審査が行われ、補助金の支払額が確定します。申請のときと同様に、電子での報告が可能な補助金もあるでしょう。
大抵の場合、完了報告は一度で終わらず、数回のやり取りをすることが多いです。受給額の確定は、「補助金額確定通知書」によって通知されます。
通知書が届いたら、今度は「補助金支払請求書」を提出します。請求書が受理されると、指定した銀行口座に補助金が支払われ、手続き完了です。
なお補助事業による関係書類は5年間の保存義務があるので、紛失しないように保管しておきましょう。
補助金関連記事 補助金対象製品一覧 工作機械 関連製品一覧工作機械の申請ならプロに相談するのがおすすめ
工作機械の補助金を申請する際は、用意すべき書類が多く、手続きにも手間がかかります。本業の傍らで情報を探しながら申請し、採択を得ようと思うと、ハードルが高いと感じるのも無理はないでしょう。自社の力だけで補助金を受給するのが困難な場合は、専門家のサポートを依頼するのも一つの手段です。主な依頼先としては、税理士・行政書士・中小企業診断士などの士業や金融機関、民間コンサルティング会社などが挙げられます。
カナデン補助金ヘルプデスクでは、補助金申請のサポートを実施中です。補助金の申請に関する最新情報をお届けすると共に、各種サポートや相談受付を行っています。申請方法など補助金に関する無料相談をお受けしているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
工作機械の導入・購入は補助金を利用しよう!
工作機械の補助金は種類や適用範囲が多いため、自社に適した補助金が見つかれば、工作機械の導入・購入にかかる費用が低減されます。また原則返済不要であることも、大きなメリットです。
しかし補助金は、申請するまでの準備に大変な労力を要します。事業計画書の作成や必要書類の準備などを本業と共に進めなければならず、企業にとって大きな負担となるでしょう。また補助金を受けられなかった場合のことを考えると、労力をかけて申請することに二の足を踏んでしまうかもしれません。
カナデン補助金ヘルプデスクでは、補助金申請に関する相談を無料でお受けしています。また補助金ごとに異なる要件や申請時期、法改正などについての最新情報をお届けし、補助金を受けたいとお考えの企業のご担当者様をサポートいたします。補助金申請でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
補助金に関するお問い合わせは次のヘルプデスクページよりお願いいたします。
補助金対象製品一覧は以下のボタンからご覧いただけます。
補助金対象製品一覧をみる