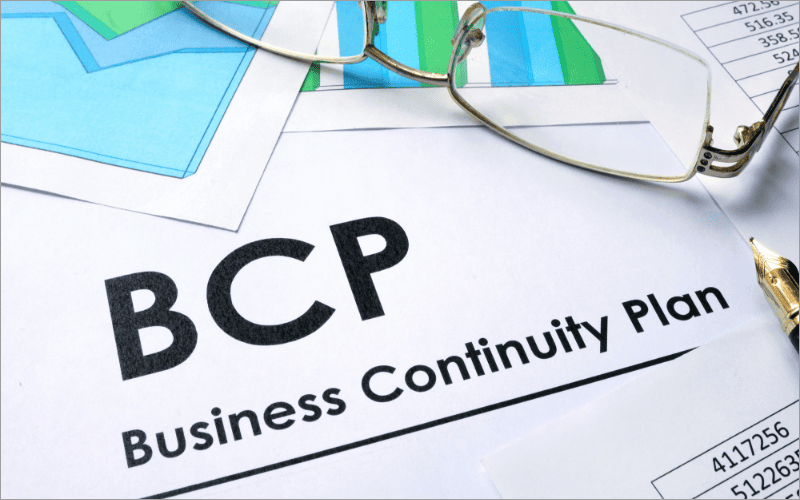BCP(事業継続計画)とは?BCMとの違いや策定のメリット・手順を解説
公開日:

地震や台風といった自然災害をはじめ、感染症のまん延や大事故、テロ等の事件、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化といった不測の事態に備えるには、緊急事態への備えが欠かせません。万が一の事態に備えて、あらかじめ策定しておく必要があるのがBCP(事業継続計画)です。
この記事では、BCPの定義や策定するメリット、日本国内における現状についてわかりやすく解説しています。BCP策定の手順や策定時に留意しておきたいポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
BCP(事業継続計画)とは
BCP(Business Continuity Plan)とは、自然災害や感染症拡大などの緊急事態が発生した際、できるだけ被害の拡大を抑制するとともに、重要な事業の継続・再開を実現するための計画のことです。はじめにBCPとBCM、災害対策といった関連用語との違いを整理しておきましょう。
BCM(事業継続マネジメント)との違い
BCM(Business Continuity Management)とは、BCPを適切に運用していくための総合的なマネジメントのことです。具体的には、次の活動がBCMに含まれています。
- BCP策定
- BCPの維持、更新
- 事業継続を実現するための予算や資源の確保
- 事前対策の実施
- 取り組みを浸透させるための教育、訓練、点検の実施
- 継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント
上記のとおり、BCP策定もBCMの一環です。BCP策定をゴールと捉えるのではなく、本来の目的どおり機能させるための総合的な取り組みがBCMといえます。
より具体的なBCP対策については次の記事もあわせてご参照ください。
災害対策・防災計画との違い
事業運営を盤石なものにするには、災害対策や防災計画を立てておくことも重要です。災害対策・防災計画とは、災害発生時に被害をできるだけ回避・軽減するための仕組みのことを指します。BCPとの大きな違いは下記のとおりです。
- 災害対策・防災計画:災害に備えて講じておく事前対策
- BCP:緊急時に資産を守るための事前/事後対策
企業は災害対策を講じるだけでなく、万が一の事態に備えて事後対策についても検討しておく必要があります。
災害対策に関しては次の記事もあわせてご参照ください。
その他の関連用語
BCPにはこの他にもいくつかの関連用語があります。BCPとの関わりや違いを押さえでおきましょう。
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| BCS | ・Business Continuity Strategy(事業継続戦略) ・BCPを実行に移すために必要な戦略のこと |
| DCP | ・District Continuity Plan(地域継続計画) ・地域の企業や自治体が連携して取り組む防災対策のこと |
| 業務継続計画 | ・BCPとほぼ同義 ・行政機関などではこの呼称を用いている場合がある |
BCPを策定するメリット
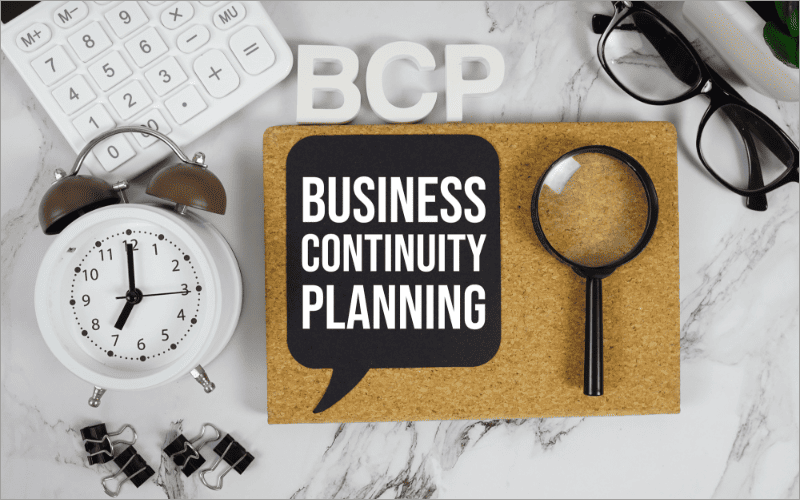
BCPの策定は、介護など一部の業界を除き、義務付けられているわけではありません。では、BCPを策定することによってどのようなメリットを得られるのでしょうか。主な4つのメリットについて解説します。
事業の停滞・縮小リスクを軽減できる
第一のメリットは、緊急事態が発生した際に事業の停滞・縮小リスクを軽減できることです。有事の際に中核事業を継続できる体制を整えておくことで、経営に致命的なダメージが及ぶのを避けられる確率が高まります。また、仮に被害に遭ったとしても早期再開に向けた動きをとりやすくなり、事業が停滞する期間を最小限に抑えられるでしょう。このように、自社にとって重要な事業を止めない・持続させるという意味において、BCP策定は不可欠な取り組みといえます。
対外的な評価を高められる
BCPを策定しておくことによって、対外的な評価が高まるというメリットもあります。緊急事態を想定して計画を立てていること自体が、ステークホルダーの信頼獲得につながるからです。万が一の事態が生じたとしても、安定的に事業を継続できる見込みがあれば、取引先としても安心して取引ができるでしょう。また、実際に緊急事態が発生した際にも事業再開に向けて迅速な動きがとれれば、信頼獲得にいっそう寄与すると考えられます。
従業員エンゲージメントの向上につながる
災害発生や感染症拡大といった緊急事態に備えて対策を講じていることは、従業員にとって大きな安心材料となります。従業員の生命を守り、事業を継続できる準備が整っているという事実そのものが、安心感や満足感の醸成につながるでしょう。BCPにもとづいて訓練などを実施することによって、こうした安心感・満足感はいっそう強固なものになっていくはずです。
業務の棚卸しを実施する機会となる
BCPを策定する過程で、既存業務を整理できるというメリットもあります。現状どのような業務があるのか、とくに優先順位の高い業務はどれであるのかを再認識し、経営戦略の進展に役立てることも可能です。現状の売上高や利益だけでなく、将来にわたって重要な事業を見極める上で、「万が一のときにどの事業を持続させるべきか」といった視点で検討することには重要な意味があります。こうした機会を得られることは、BCP策定に取り組む大きなメリットといえるでしょう。
日本国内におけるBCPの現状

ところで、日本国内の企業は現状どの程度BCP策定を進めているのでしょうか。大企業・中堅企業の状況と、中小企業・小規模事業者の状況についてそれぞれ解説します。
大企業・中堅企業のBCP策定状況
大企業のうち、2023年度の時点でBCP策定が完了している事業者は全体の76.4%、中堅企業に関しては全体の45.5%です。裏を返すと、大企業の4社に1社、中堅企業の2社に1社がBCP未策定の状況となっています。緊急事態を想定した計画を平時から立てている企業と、未実施の企業に二分化しているのが実情です。大企業・中堅企業においてBCPを策定していない場合は、早急に計画を立てておく必要があるでしょう。
※出典:内閣府「令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/chosa_240424.pdf
中小企業・小規模事業者のBCP策定状況
中小企業・小規模事業者に関しては、2023年度の時点でBCPを策定している企業は15.3%です。多くの企業はBCPを策定できていない状況が見て取れます。
実は、中小企業や小規模事業者ほど緊急事態に備えておく必要があります。とくに資金に余裕がないケースや、設備等が限られているケースにおいては、有事の際に事業の継続そのものが危ぶまれることにもなりかねません。BCPについて早急に検討をはじめ、策定を完了させておくのが望ましいでしょう。
※出典:中小企業庁「2024年版 中小企業白書・小規模企業白書概要」https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240510002/20240510002-1.pdf
BCP策定の手順
ここからは、BCPを策定する際の基本的な手順について見ていきます。BCPは計画書を記入すれば完成するわけではありません。次の手順に沿って、実効性のある計画を立てていくことが重要です。
1. BCP策定の方針を明確化する
はじめに、自社がBCPを策定するにあたって方向性を定めておく必要があります。経営方針や基本理念、事業計画などに立ち返り、自社が目指すべき姿を明確にしておきましょう。
その上で、BCPをなぜ策定する必要があるのかじっくりと検討することが重要です。BCPを経営方針や理念と切り離して、単独で作成することがないよう注意してください。
2. 事業上、重要な製品・業務の優先順位をつける
次に、自社の中核事業を再確認し、優先的に継続を目指すべき事業を特定します。事業全体の継続・復旧を実現するのが理想ですが、状況によっては重大なダメージを受けることも想定されるからです。売上を支えている重要な製品や業務を見極め、優先順位をつけましょう。
たとえば、自社の方針として今後育てていきたいブランドがあるとします。このブランドに関連する業務が長期間停止を余儀なくされたり、廃止せざる得なくなったりするのは会社にとって大きな痛手です。このように現状の売上規模だけでなく、中長期の方針との整合性を踏まえた上で事業の重要度を判断する必要があります。
3. 発生し得る災害とその影響を調査する
自社が直面し得るリスクを、過去に発生した災害の記録やハザードマップなどを元に調査していきます。実際にそれらのリスクに見舞われた際、どの程度の影響を受ける可能性があるか、被害を最小限に抑えるにはどういった対策が求められるのかを整理しておきましょう。
一例として、大震災が発生した際にどのようなリスクが想定されるのかを洗い出すのは有効な方法といえます。社内の設備や機器が揺れに耐え得る強度で固定されているか、避難経路は確保されているか、避難場所は明確になっているかといった点を実際に震災が起きた場合を想定して検討しておくことが大切です。
4. BCP様式を参考に計画書を作成する
洗い出したリスクとその対策を、計画書にまとめていきます。BCPは自社で一から作成するよりも、既存の様式を活用するほうが漏れなく効率的に作成しやすいでしょう。
例えば、内閣府の「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例」や中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」などを参考にすると、様式や構成を考える上で役立ちます。
計画書に落とし込む際には、次の5つの視点でまとめていくのが得策です。
- 人的リソース:業務を担う人材を確保できるか
- 施設・設備:被害を最小限にとどめ、復旧を目指せるか・代替手段はあるか
- 資金調達:資材の調達や設備・建物の修復、買い替えに必要な資金は確保できるか
- 体制・指示系統:誰がどのような方法で、誰に対して指示を出すのか
- 情報:どのような情報が必要とされるのか
なお、資金面に関しては必要に応じて補助金や助成金の活用も検討するとよいでしょう。非常用電源の導入にも補助金を活用できる場合があります。詳細は次の記事を参考にしてください。
5. 必要な体制を整備し訓練を実施する
完成したBCPに沿って体制を整備し、定期的に訓練を実施します。十分に検討を重ねた上で作成されたBCPであっても、実際に行動してみると漏れが見つかったり、改善が必要な課題が発見されたりするものです。訓練を通じて浮上した課題についてはあらためて対応策を検討し、BCPを適宜更新しましょう。
また、組織変更時や国、業界のガイドライン等が改定された際には、BCPも連動したものになるよう見直す必要があります。BCPに古い組織図がそのまま反映されていたり、異動前の担当者や責任者が記載されていたりすることのないよう注意が必要です。
BCP策定のポイント

BCPを策定する際に意識しておきたいポイントを紹介します。実効性のあるBCPにするためにも、次の3点を必ず押さえておきましょう。
自社の実態に即した計画を立てる
BCPに「正解」や「決まった形」はありません。肝心なことは、いざというときに自社の中核事業を継続できるかどうかです。したがって、自社の実態に即した計画になっているかどうかは常に注意を払う必要があるでしょう。
たとえば、実際には存在しない「外部パートナー企業」との協力体制を前提とした計画になっているようでは、実効性がないといわざるを得ません。現実的に対応できる範囲でBCPを策定できるよう、必要に応じて現場の意見も取り入れながら検討していくことが重要です。
国が公開している各種資料を参照する
内閣府や中小企業庁は、BCP関連の資料を公開しています。先に紹介した「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例」や「中小企業BCP策定運用指針」の記載例をベースに作成するとよいでしょう。また、公開されている「記入シート」などを適宜活用することで、記載すべき事項の抜け漏れを防ぐ効果も期待できます。
はじめから完璧を目指さない
BCPはあらゆるリスクを想定して策定するのが理想ですが、実際には最初から完璧な計画を立てるのは容易ではありません。中核事業を見極め、優先順位をつけて取り組むことが大切です。
たとえば停電時の非常用電源を確保する際には、全事業所のすべての電源を平常どおり利用できるようにするのは困難なケースが想定されます。この場合、重要業務に絞って必要最小限の電力確保を目指すことで、より現実的な対策を講じられる可能性が高まるでしょう。
製造業のBCP策定のポイントは次の記事でも説明していますので参考にしてください。
BCPに関するよくある質問
はじめてBCPを策定する際にはさまざまな疑問が浮かんでくるものです。BCPに関するよくある質問をQ&Aにまとめました。
BCPとBCMはどう違うのですか?
- BCP:緊急事態の発生時に被害の抑制と中核事業の継続・復旧を実現するための計画
- BCM:BCPを適切に運用していくための総合的なマネジメント
BCP策定は企業にとって義務ですか?
BCP策定は、福祉施設に関しては2024年4月より義務化されています。したがって、福祉施設を運営する事業者は必ずBCPを策定しなければなりません。一方、BCP策定が現状義務化されていない業種であっても、有事に備えた対策が推奨されています。BCP策定によって対外的な評価や従業員エンゲージメントの向上につながるほか、業務の棚卸しを実施する機会にもなることを踏まえると、業種を問わず策定しておくのが望ましいでしょう。
BCPの意義を理解した上で策定・運用に取り組もう
地震や台風といった自然災害をはじめ、感染症のまん延や大事故、テロ等の事件、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化といった事態は、いつ発生するのか予測できません。緊急事態に直面しても中核事業を継続・復旧できるよう、BCPを策定しておくことが大切です。BCPには有事に備えた計画という意味合いのほか、平常時からリスク管理への意識を向上させるという意味合いの2つの側面があります。今回紹介したBCP策定の手順や策定時のポイントを参考に、自社にとって必要な計画書を作成してください。
【災害発生時の被害の抑制・防止に役立つ製品例】
カナデンでは、いつ起こるかわからない自然災害や緊急事態に備え、お客様の事業を止めないためのBCP対策を多角的にサポートしています。災害時の電源確保に不可欠な非常用電源装置から、重要な設備を保護する避雷針システムまで、豊富な製品ラインナップとこれまでに培った知見を活かし、お客様一人ひとりの課題に寄り添った最適なソリューションをご提案します。