EV充電インフラ、国の拡大政策でどう変わる?製造業・工事業の皆様が知るべきポイント
2025年8月22日
製品・サービス紹介
- 製品・サービス

近年、電気自動車(EV)の普及が加速する中で、充電インフラの整備は喫緊の課題となっています。特に製造業や工事業に携わる皆様の中には、EV導入を検討されている方や、既に導入済みで充電環境に課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、経済産業省が掲げる「充電インフラ整備促進に向けた指針」を基に、EV充電インフラがどのように変化していくのか、そのポイントを詳しく解説いたします。
※以下記事、全て出展:
EV充電インフラ整備の現状と課題
これまでのEV充電インフラ整備は、「グリーン成長戦略」に基づき、2030年までに公共用の急速充電器3万口を含む15万口の充電インフラ設置を目標に進められてきました 。しかし、EVのさらなる普及を見据えると、充電インフラの質と量の両面で、多くの課題が見えてきています 。
主な課題としては、以下の点が挙げられます 。
・充電器の設置数や出力の不足
・充電事業の継続性(採算性)
・社会全体での費用負担
・充電に関する不具合
・ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの対応不足
これらの課題を解決し、利便性が高く持続可能な充電インフラ社会を構築するため、新たな指針が策定されました 。
「充電インフラ整備促進に向けた指針」の3つの原則
経済産業省が策定した「充電インフラ整備促進に向けた指針」は、以下の3つの原則を総合的に考慮しながら、充電インフラ社会の構築を目指しています 。
・ユーザーの利便性の向上
・充電事業の自立化・高度化
・社会全体の負担の低減
これらの原則に基づき、2030年までの整備目標が大幅に引き上げられました 。

充電器設置目標の倍増:2030年までに30万口へ
従来の目標であった15万口から倍増し、2030年までに公共用の急速充電器3万口を含む充電インフラ30万口の整備を目指します 。これは、新車販売の市場規模やEV普及の見通し、住宅環境や車両の特性などを総合的に勘案した結果です 。
高出力化の推進:平均出力80kWを目指す
充電時間の短縮は、ユーザーの利便性向上に直結します 。そのため、急速充電の平均出力を現在の約40kWから2倍の80kWまで引き上げ、充電器全体の総出力を現在の約39万kWから10倍の約400万kWを確保することを目指します 。
特に高速道路では、90kW以上の高出力急速充電器を基本とし、需要の多い場所では150kWの急速充電器も設置する方針です 。これにより、短時間での充電が可能となり、長距離移動の際の利便性が向上します 。
効率的な充電器設置と費用対効果
限られた補助金を効果的に活用するため、費用対効果の高い案件を優先する仕組み(入札制の実施など)を導入し、充電事業の自立化を促進します。

電力量(kWh)に応じた課金方式の導入
2025年度からのサービス実現を目指し、充電した電力量(kWh)に応じた課金(従量制課金)が広範に導入されることを目指します 。これにより、ユーザーは充電した量に応じて料金を支払うことになり、納得感が高まります 。
設置場所ごとの充電インフラ整備
指針では、設置場所ごとの特性に応じた整備方針が示されています。
急速充電(公共用、主に経路充電)
高速道路のサービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)では、原則として1口あたりの出力を90kW以上とし、2025年度までに1100口程度、2030年には2000〜2500口の整備を目指します 。また、充電器の稼働率にばらつきがある現状を踏まえ、高速道路では概ね70km間隔で充電器が整備されるよう目安が示されました 。
道の駅、ガソリンスタンド(SS)、コンビニ、自動車ディーラーなどにおいても、駐車スペースに余裕がある場合や充電ニーズが高い箇所は、1口の出力が90kW以上で複数口に対応した充電器の設置を行い、難しい場合でも50kW以上の出力を確保します 。
普通充電(公共用目的地充電)
商業施設やレジャー施設などの目的地に設置される普通充電器は、滞在中にコストを抑えて充電できるというメリットがあります 。2030年には10万〜15万口の設置を目安としており 、稼働率などのデータを考慮しながら、必要性の高い施設への設置を具体化していく方針です 。
普通充電(集合住宅等における基礎充電)
集合住宅でのEV充電は、特に既築(きちく)物件で管理組合の合意形成が必要なため、設置が進みにくい現状があります 。今後は、既築・新築ともに、集合住宅への充電器整備を促進し 、2030年には集合住宅や月極駐車場などで10万〜20万口の設置を目指します 。
商用車向けの充電インフラ
EVバスやEVトラックなどの商用車は、乗用車に比べて電池容量が大きく、夜間など特定の時間帯に充電が集中しやすいという特徴があります 。そのため、運行計画とエネルギーマネジメントを事前に検討した上で、計画的に車両導入と充電器設置を進めることが重要とされています 。
多様な利用形態を実現するための取り組み
ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応
不特定多数が利用する公共用充電施設では、車椅子利用者を含め幅広い人々が利用できるよう、ユニバーサルデザイン(UD)・バリアフリー対応を進めます 。経済産業省と国土交通省が連携し、ガイドラインを策定し、取り組みを促します 。特に高速道路のSA・PAや道の駅においては、急速充電器の新設時や更新時を中心に、UD・バリアフリーに対応した充電器・区画の整備を進めます 。
充電器の通信規格のオープン化
公共用の充電器については、欧米の標準化動向や国内事業者のニーズを踏まえ、OCPP(Open Charge Point Protocol)といったオープンプロトコルの通信規格を推進します 。具体的には、2025年度から、充電器(受電装置)が遠隔で管理・運用ができる機能を持ち、かつ充電器(受電装置)へのOCPPの搭載を補助の要件としていくとしています 。これにより、充電事業者が変更された場合でも充電インフラを引き続き利用できるなど、ユーザーの利便性や事業者の運用効率が向上します 。
まとめ
今回の「充電インフラ整備促進に向けた指針」は、EV普及を加速させるための国の強い意志を示すものと言えるでしょう 。充電インフラの量と質の向上が図られることで、製造業や工事業の皆様にとっても、EV導入のハードルが下がり、よりEVを事業に活用しやすい環境が整っていくことが期待されます。
弊社では、こうした国の政策動向も踏まえ、お客様のニーズに合わせた最適な充電インフラソリューションをご提案してまいります。EV導入や充電環境の整備にご興味がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※出典:経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」(令和5年10月)https//www.meti.go.jp/press/2023/10/20231018003/20231018003-1.pdf



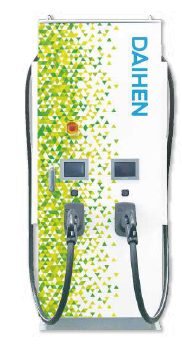
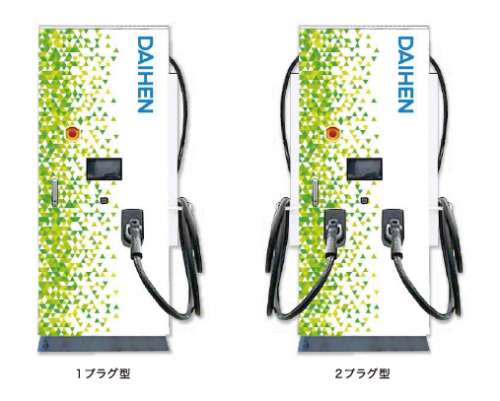



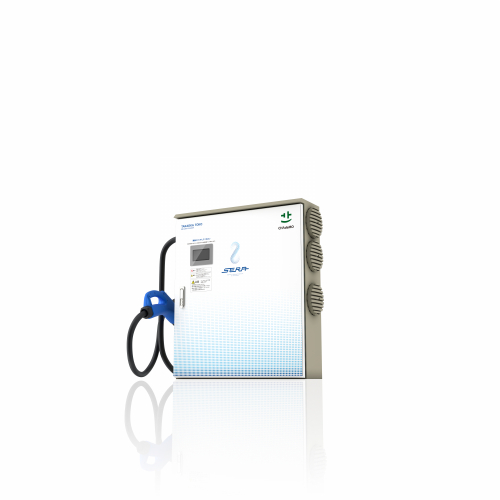
_jpg_w500px_h333px.jpg)
