工場DXとは?推進するメリットや課題、成功事例、役立つツールを紹介
公開日:

近年、幅広い業界がDX推進に注力しています。工場も例外ではなく、人手不足の解消や国際競争力の維持・伸長、柔軟な生産体制の確立に向けてDX推進が求められているのが実情です。
この記事では、工場DXを推進するメリットや直面しやすい課題のほか、工場DXに役立つツール例をわかりやすく解説しています。工場DXの成功事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
工場DXとは
はじめに、DXの基本的な定義や工場DXが求められている理由を整理しておきましょう。従来の「改善活動」との違いを理解しておくことが大切です。
そもそもDXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な定義を、経済産業省は次のように表しています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
※出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf
トランスフォーメーションという言葉には「変革」「変化」といった意味があります。単にデジタル化を実現するだけでなく、ビジネスモデルや業務のあり方そのものに変革をもたらす取り組みと捉える必要があるでしょう。
工場DXが求められている理由
工場DXが求められている主な理由として、次の3点が挙げられます。
人手不足の解消
少子高齢化が急速に進む日本においては、生産年齢人口(労働人口)はすでに減少に転じています。かつてのように「募集をかければ応募者が集まる」という時代ではなくなりつつあり、業界・企業間での人材獲得競争が激化しているのが実情です。より少ない人員で生産量や品質を維持していく上で、機械化・自動化は避けて通れない課題といえるでしょう。
国際競争力の維持伸長
国際競争力を維持していく上で、DX推進が欠かせないという面もあります。産業は急速にグローバル化しており、諸外国の企業と価格や品質面で真っ向から勝負する時代になりました。高い品質を保ちつつコスト削減を図るためにも、より合理的・効率的な生産体制の確立が求められています。
柔軟な生産体制の確立
製品を「より早く」「より無駄なく」製造することが求められている現代において、柔軟な生産体制を確立する必要に迫られていることも要因の1つです。従来の業務プロセスやビジネスモデルを本質的に見直し、変革を目指していく上で、データにもとづいた的確な判断や意思決定が求められています。
改善活動との違い
DXと明確に分けておく必要があるのが、工場で従来実施されてきた「改善活動」です。改善活動とは、作業の効率化やコスト削減といったように、現状の製造工程を「より良くするための活動」といえます。
一方、DXは既存の業務プロセスやビジネスモデルにこだわらず、抜本的な変革を目指す取り組みのことです。DXが従来の改善活動にとどまることのないよう、目指すべきゴールの違いを明確に捉えておく必要があります。
工場DXを推進するメリット
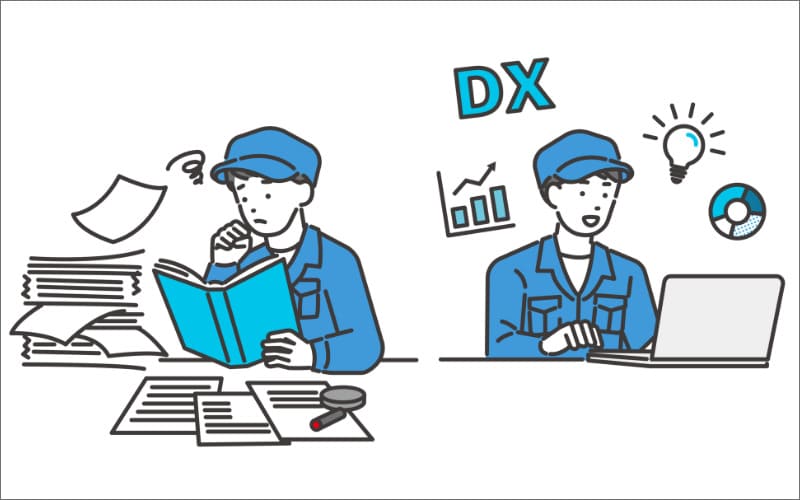
工場DXを推進することによって、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。主な5つのメリットについて解説します。
生産工程の効率化につながる
1つ目のメリットは、生産工程の効率化につながることです。稼働状況などのデータを可視化して共有することにより、業務効率化が可能なポイントが明確になります。直感や経験則にもとづく効率化の方策は、必ずしも効果を生むとは限りません。定量的なデータを収集・分析することによって、ボトルネックとなっている工程を特定しやすくなるほか、故障や不具合が生じる可能性の高い箇所を予測しやすくなる点がメリットです。
生産コストを抑制できる
生産コストの抑制に寄与することも、DX推進によって得られるメリットの1つです。工場内で稼働している設備のデータを収集することによって、顕在化していない3M(無理・無駄・ムラ)を発見できる確率が高まります。必ずしも人が担う必要がない作業は機械化・自動化を進めることで、生産コストを圧縮できるでしょう。結果として利益率が向上し、より利益体質の工場へと生まれ変わっていくことが期待できます。
省力化・省人化につながる
効率化や自動化を推進することによって、省力化・省人化につながることも大きなメリットといえます。より少人数で従来と同じ業務を遂行できたり、より少ない負担で生産量を維持できたりすれば、人的リソースに余力が生まれるでしょう。こうして余裕ができた人的リソースを生産性の高い業務に割り当てることで、さらなる品質向上や事業拡大を目指せます。
工場の省人化・少人化については、次の記事もあわせてご参照ください。
▶工場の省人化・少人化とは?成功事例や省力化との違いをわかりやすく解説
人的ミスを未然に防げる
作業工程の自動化・半自動化を推進することは、人的ミスの抑制にも寄与します。人が担う業務にはミスが付き物です。人手を必要とする工程を極力減らしていくことが、人的ミスを防ぐための効果的な対策といえるでしょう。判断ミスや操作ミスによる歩留まりが抑制されることは、製造コストの削減や生産性の向上を実現する上でも重要なポイントです。
作業工程の属人化を防止できる
工場DXの推進は、作業工程の属人化を防ぐ意味においても有効です。データにもとづいて判断することによって、特定の担当者の直感や経験に頼らざるを得ない工場運営から脱却できます。作業工程を標準化することで、人材育成に要するコストや時間を削減できることも大きなメリットです。結果として持続可能な経営の実現につながり、将来にわたって安定的な事業運営を続けやすくなるでしょう。
工場DXで直面しやすい課題

工場DXを推進するにあたって、さまざまな課題に直面することが想定されます。とくに直面しやすい3つの課題と対処策を把握しておきましょう。
既存の設備・システムとの統合
工場DXを推進する上で重要なポイントとなるのが「データの一元化」です。工場内の設備・機器から稼働データなどの各種情報を収集し、一元管理することによって合理的な意思決定が可能になります。
一方で、既存システムからどのようにしてデータを収集するのかが課題となりがちです。センサーなどのIoTを活用することで、既存設備と新たなシステムの統合を図る必要があるでしょう。製造業におけるIoTの重要性や活用事例については、次の記事もあわせて参考にしてください。
▶製造業におけるIoTの重要性とは?活用事例・低コストでの導入方法をご紹介
デジタル人材の不足
データやIT機器を扱えるデジタル人材の確保も、工場DXに際して直面しやすい課題の1つです。工場DXそのものを計画・実行するには、従業員のスキル向上が求められます。
また、現場で機器やツールを使いこなすためのスキルを従業員に身につけてもらわなければなりません。機器やツールの導入をゴールと捉えるのではなく、導入後にスムーズな運用を実現し、活用を定着させていくことが重要です。そのためには、デジタルツールを導入するだけでなく工場での実務に精通している人材にDXスキルを身につけてもらう必要があるでしょう。
自社に適したツールの選定
自社の課題解決につながるツールを見極め、選定するための知見が求められるという課題もあります。ツールは機能が豊富になるほど使いやすくなるとは限りません。むしろ、自社にとって不要な機能が多く備わっているツールは操作方法が複雑になったり、無駄なコストが発生したりしがちです。
こうしたリスクを回避するには、自社の解決すべき課題を整理し、課題解決に役立つツールを選定する必要があります。数多くあるツールの中から目的に合ったものを見極められるかどうかは、工場DXの成否を分ける鍵といっても過言ではないでしょう。
工場DXに役立つツール
工場DXに役立つツールの例を紹介します。それぞれ何を実現できるのか、どういった導入メリットがあるのかを確認しておきましょう。
予知保全(予兆保全)関連ツール
予知保全とは、設備や機器の故障・不具合の兆候が現れていることを検知し、通知することです。具体的には設備・機器の温度変化を察知するサーモカメラや、通常とは異なる振動を検知する振動センサなどが用いられます。こうしたツールを導入することで、外観や音では認識できない不具合の兆候を早期に発見しやすくなるため、メンテナンスコストの削減や工場の安定稼働につながるでしょう。
【予知保全(予兆保全)ツールの例】
稼働監視・遠隔監視関連ツール
稼働監視とは、工場の生産ラインや設備の稼働状況をリアルタイムで監視する取り組みのことを指します。遠隔地に設置したカメラやセンサーで収集したデータを、インターネット経由で確認する取り組みが遠隔監視です。こうした取り組みにより、点検やメンテナンス業務の省人化や迅速な異常検知に役立つほか、予知保全の精度を高める効果が期待できます。
【稼働監視・遠隔監視ツールの例】
OTセキュリティ関連ツール
OT(オペレーショナルテクノロジー)は、産業プラントや社会インフラなどの設備・システムを制御・運用する技術の総称です。こうした設備・システムへの物理的な攻撃や、制御システムへの不正アクセスを防ぐための対策をOTセキュリティといいます。OTセキュリティの強化は、工場の安全な運用と安定稼働のために欠かせない対策といえるでしょう。
OTとITの違いや、両者を連携させる際の注意点については次の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
▶OTとITの違いは?システムやセキュリティに関する違い、連携にあたっての注意点などを解説
工場DXの成功事例

さまざまな設備やツールを効果的に活用し、工場DXに成功した事例を紹介します。導入した技術と導入効果をまとめていますので、自社でDXを推進する際の参考事例として役立ててください。
事例1:異常発生の状況をいち早く確認・分析
カメラ映像とSCADAを連携し、異常発生時の状況をいち早く確認・分析するための仕組みを構築した事例です。異常発生時の映像を確認することで、原因究明やチョコ停復旧に役立ちます。また、作業の標準化に際して作業工程の課題を抽出するための資料としても有効です。ヒヤリハットの記録やアラーム発報によって、事故の防止につながる効果も得られました。
【異常発生の検知に役立つ製品の例】
事例2:保守やメンテナンスなどの紙帳票を電子化
紙帳票を電子化し、ペーパーレスと効率的な作業管理を実現した事例です。現場のタブレットから点検データや作業記録を電子帳票に入力できるようになったことに加え、入力された情報がリアルタイムで共有されるようになったため、管理業務の効率化につながりました。また、転記ミスなどの人的ミスの抑制や、蓄積データにもとづく分析に役立つことも大きなメリットの1つです。
【ペーパーレス化に役立つ製品の例】
事例3:ロボットパーツの消耗度を監視
ロボットの状態監視により予知保全を実現し、突発的なダウンタイムを回避している事例です。モータの劣化や関節消耗度からメンテナンス時期を予測し、予知保全をサポートする仕組みを構築しました。各軸サーボモータからのフィードバック値と状態を伝えるメッセージが表示されるため、パーツの交換時期を予測して計画的にメンテナンスを実施できています。
【予知保全に役立つ製品の例】
工場DXのよくある質問
工場DXに関するよくある質問をQ&Aにまとめました。
工場DXとは何をすることですか?
工場DXとは、データやデジタル技術を活用して製造工程や業務のあり方に抜本的な変革をもたらす取り組みのことです。少子高齢化が急速に進む日本において、人手不足の解消や国際競争力の維持・伸長、柔軟な生産体制の確立に向けて欠かせない取り組みといえます。従来の「改善活動」が現状の製造工程をより良くするための活動であるのに対して、工場DXは既存の業務プロセスやビジネスモデルに囚われず、抜本的な変革を目指す取り組みである点が大きな違いです。
工場DXが進まない理由は?
工場DXは重要な取り組みとされている一方で、実際にはあまり進んでいないケースも多く見られます。その主な理由として挙げられるのは次の3点です。
- 既存の設備・システムとIoTの連携が壁になっている
- 工場DXを計画・実行するために必要なデジタル人材が不足している
- 現場の課題を解決するためのツールの選定が容易でない
工場DXは単に設備やツールを導入すれば実現できるものではありません。上記の課題を1つずつ解決し、データやデジタル技術を効果的に活用するための計画を立てて臨む必要があります。
工場DXをスモールスタートから実現しよう
工場DXは既存の業務フローを抜本的に変革していくための取り組みであり、従来の「改善活動」とは異なります。工場DXによって自社が現状抱えている課題を一度に解決できるのが理想ですが、実際には優先度の高い課題から着手するのが得策でしょう。まずはスモールスタートから工場DXに取り組み、徐々に適用範囲を広げていくことをおすすめします。今回紹介したツール例や成功事例を参考に、自社の課題解決につながる工場DXを推進してください。
「業務効率を改善したい」「生産性を向上させたい」といったお悩みはありませんか?
カナデンは、お客様の状況に合わせた最適なDX・業務改善ソリューションで、そのお悩みを解決します。詳しい内容や導入事例については、










