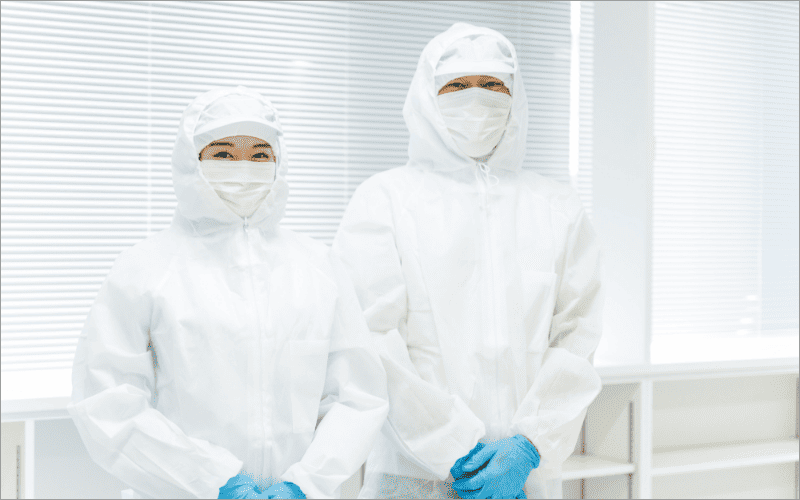HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは?小規模事業者が抱えるリスクや実践方法も紹介
公開日:
2021年6月1日より、国際的な衛生管理基準であるHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が原則として全ての食品等事業者に義務付けられました。小規模事業者にも「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(※)に基づく取り組みが求められますが、運用面で課題を抱えるケースも少なくありません。
そこで本記事では、HACCPに沿った衛生管理の概要や小規模事業者が直面しやすい潜在リスク、実践に役立つ具体的な方法を解説します。本記事を参考に、衛生管理体制を見直し、安心と信頼を届けられる体制の構築に役立ててください。
- 小規模事業者向けのHACCPに基づいた衛生管理の基本
- 小規模事業者が抱えやすい衛生管理上の潜在リスク
- 衛生管理の実践方法と役立つ設備・機器
※出典:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/01_00019.html
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは?
HACCPは「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略称で、日本語では「危害分析重要管理点」と呼ばれます。国際的な衛生管理基準で、原材料の確保から最終製品まで、製造の各工程で食品事故につながるリスクを予測して管理方法を明確化し、特にリスクが高い工程はより厳格な管理を行うものです。
日本では食品衛生法の改正により、2021年6月1日から小規模事業者を含めた全ての食品等事業者を対象に、HACCPに沿った衛生管理が原則として完全施行となりました(※)。
HACCPに基づく衛生管理は、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があります。 このうち、小規模事業者に義務付けられているのは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」です。 ただし、小規模事業者であっても、より高度な衛生管理を行いたい場合は、「HACCPに基づく衛生管理」を採用しても構いません。
なお、より大規模な食品工場などで求められる「HACCPに基づく衛生管理」や、その土台となる一般衛生管理については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶食品工場の衛生管理を徹底するには?HACCPや一般衛生管理、実践方法まで徹底解説
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる小規模事業者は、以下の通りです(※)。
- 食品を製造・加工する施設に併設・隣接される店舗で製造・加工した食品の全てもしくは大部分を小売販売する営業者
- 飲食店・喫茶店などで提供する食品を調理する営業者
- 容器包装された食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者
- 食品を分割して容器包装し、小売販売をする営業者
- 食品を製造・加工・貯蔵・販売・処理する営業者のうち、食品などの取り扱いに関わる従業員数が50人未満の事業場
上記に該当する事業者は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を認めた手引書に沿って、以下の内容を実施することで、HACCPに沿った衛生管理が実施できていると見なされます。
- 手引書を読み、自分の業種・業態において想定される危害要因を把握する
- 手引書にあるひな形を活用し、衛生管理計画を作成する(必要に応じて手順書も作成する)
- 作成した衛生管理計画や手順書の内容を従業員に周知し、理解・実践を促す
- 手引書の記録様式を用い、衛生管理の実施状況を継続的に記録する
- 手引書で推奨される期間、記録を適切に保存する
- 記録などを定期的に確認し、必要に応じて衛生管理計画や手順書を更新する
※出典:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/01_00019.html
小規模事業者が直面する衛生管理の潜在リスク

小規模事業を経営する方や、品質管理を担当している方の中には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の概要を理解していても、対応においてさまざまな悩みや課題を抱えている方もいるのではないでしょうか。
ここからは、小規模事業者が直面しやすい衛生管理の潜在リスクについて解説します。
従業員への教育不足によるリスク
小規模事業者が抱える潜在的なリスクの一つに、従業員教育の不足があります。
衛生管理を確実に実施するためには、全ての従業員が高い衛生意識を持ち、日々の業務でそれを実践することが不可欠です。しかし現実には、従業員全員の意識を同じレベルに保つことは簡単ではありません。意識が低い従業員がいると、手洗いが不十分になったり、衛生基準に合わない服装で作業したりしてしまい、衛生管理全体のレベルが低下してしまうでしょう。
例えば、正しく手洗いできていない場合、手に付着した菌が食品を汚染し、食中毒のリスクが上昇します。また、適切で清潔な服装が徹底されていなければ、体毛や汗、ほこりなどの異物が混入する可能性も高いです。
加えて、衛生管理を徹底するためには、従業員一人ひとりの健康管理も重要です。例えば、体調不良の場合、責任者に報告し、適切な対応を取ることが求められます。しかし、その際の対応を事業所でルール化していても、事実を隠して働いてしまう従業員もいるかもしれません。その結果、食品はもちろん、他の従業員に感染が広がるリスクも高くなってしまいます。
従業員の意識向上には、適切な教育の実施が効果的ですが、教育体制が整っていなかったり、教育に割く時間を確保できなかったりするケースも少なくありません。
空気質の管理不足によるリスク
空気質の管理不足によって、食品事故のリスクが高まることもあります。
空気中には目に見えないさまざまな細菌が浮遊しています。一見問題ないように思えても、空気中の細菌が食品に付着すると、食中毒を発生させてしまうリスクが高いです。
また、室温や湿度を適切にコントロールできていないことで、細菌が増殖し、食品事故につながることもあります。十分な換気ができておらず、結露が発生すれば、水滴が製品に落ちて細菌やカビが増殖してしまうケースも少なくありません。水滴は機器の劣化の原因にもなるため、コスト面でも影響が出てしまいます。
細菌による食中毒のリスクを軽減するために、殺菌効果のある照明を導入している事業場もあるでしょう。しかしこの場合、万が一照明が破損・落下してしまうと、ガラス片が食品に混入するリスクもあります。また、発熱量が多い照明の場合、施設内の温度を上昇させてしまい、食品の質や細菌の増殖に影響してしまう可能性も高いです。
運営管理不足によるリスク
運営管理不足によるリスクも、小規模事業者が直面しやすい問題です。
前述した通り、小規模事業者は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の手引書に沿って定められた規定を満たすことで、HACCPに沿った衛生管理が行われていると見なされます。
衛生管理の記録は作成した衛生管理計画に沿って、毎日行わなければなりません。また、手引書では振り返りの頻度は示されていませんが、一般的には1カ月に一度を目安に、定期的な振り返りを行うことが望ましいです。振り返りの内容によっては、計画の見直しも行う必要があります。
しかし、衛生管理の重要性を理解していても、忙しさから後回しになり、運用や改善が不十分になるケースも考えられます。その結果、手引書に沿った対応をしていても、漏れやミスが発生してしまうかもしれません。
管理が不十分な状態が続けば、食品事故につながる重要な兆候を見逃しやすくなるため、事故が発生するリスクが高まってしまいます。
【事例で学ぶ】HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実践方法
HACCPの考え方を取り入れて衛生管理を行うには、具体的にどのような取り組みをすれば良いのでしょうか。
ここからは事例を交えて、HACCPの考え方に準じた衛生管理の実践方法を解説します。
従業員一人ひとりの衛生意識と行動を徹底させる
まず従業員一人ひとりの衛生意識と行動を徹底させましょう。
前述した通り、正しい手洗いや適切で清潔な服装を継続できるかは、従業員個人の意識が大きく影響します。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に沿った衛生管理を行うには、衛生管理計画や手順書の内容を従業員に周知する必要がありますが、それだけで従業員全員の意識が向上するわけではありません。
個人の意識を向上させるためには、適切な衛生教育を行うことが大切です。衛生管理をルール化して伝えることはもちろん、「なぜそのルールが重要なのか」「ルールを守らなかった場合、どのようなことが起こるか」も伝えることで、従業員一人ひとりが「自分ごと」として意識しやすくなります。
また、食品衛生の現場では、以下の「7S」を徹底することが推奨されています。
- 整理:必要なものと不要なものを区別し、不要品を処分する
- 整頓:器具などの収納場所を決め、決められた場所にしまう
- 清掃:作業環境の汚れやごみはその都度取り除く
- 洗浄:器具や設備はその都度洗浄し、汚れの付着を防ぐ
- 殺菌:器具や設備は殺菌・除菌を行う
- しつけ:整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌を習慣づける
- 清潔:上記6Sを徹底し、清潔な状態を維持できる
この7Sを徹底するために、作業手順をルール化し、従業員全員に遵守させることも大切です。
ただし、衛生管理に関するルールを周知徹底しても、時間の経過とともに効率や売上を優先してしまい、ルールが形骸化してしまうケースは少なくありません。衛生環境を維持し続けるには、定期的に衛生教育を実施し、従業員の意識を高めることが大切です。
ここからは、従業員の衛生教育の中でも特に意識すべき「手洗い」と「作業服」について解説します。
二次汚染を防ぐために手洗い・乾燥の質を高める

従業員の手から食品への二次汚染を防ぐためには、手洗いの徹底に加え、乾燥の質を高めることが重要です。
まず手洗いは、全従業員が衛生的手洗いを徹底できるように指導しましょう。衛生的手洗いとは、アルコール消毒液や石けんを用いた手洗いのことです。
【正しい手洗い方法】
- 流水で手を洗う
- 洗浄剤を手に取る
- 手のひら、指の腹面を洗う
- 手の甲、指の背を洗う
- 指の間(側面)、股(付け根)を洗う
- 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う
- 指先を洗う
- 手首を洗う(内側・側面・外側)
- 洗浄剤を十分な流水でよく洗い流す
- 手をふき乾燥させる
- アルコールで消毒する
手洗いは、作業前やトイレの後、休憩後はもちろん、以下のタイミングでも行います。
- 生鮮食品に触った後
- 扱う食品が替わるとき
- それ以降加熱を行わない食品を触る前
- 盛り付け・配膳前
- 顔や体、髪の毛などを触った後
- 段ボールやごみ、ごみ箱などを触った後
- 清掃後
- エプロンや布巾などに触れた後
- 接客後
二次汚染を防止するためには、洗った後の手を徹底して乾燥させることも重要です。手洗いによって手に付着した細菌を減らすことができますが、ぬれた手のままは、乾燥した手に比べて細菌が増殖しやすいとされています。またアルコールで殺菌しても、ぬれたままの手では、期待される効果が得られません。
手をしっかり乾かすにはペーパータオルを使う方法がありますが、ハンドドライヤーもおすすめです。ハンドドライヤーは、ペーパータオルよりもランニングコストを抑えられる上、ごみを減らすこともできます。
小規模事業者でも、作業場への入室準備室などにハンドドライヤーを導入している事業場は多いです。
例えば三菱電機住環境システムズ株式会社 の「衛生強化モデル」のハンドドライヤー『ジェットタオルⓇ』は、「水滴飛散抑制ノズル」を搭載していて、利用者への水滴の飛び散りを99.9%まで抑えながら、効率的に手を乾燥させられます(※2)。また「ヘルスエアーⓇ機能」も持つので、設置箇所の空気も浄化でき、空気質の向上にも役立ちます。
※1 出典:厚生労働省「できていますか?衛生的な手洗い」https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf02.pdf
※2 色水を用いて水滴飛散量を確認(三菱電機株式会社調べ)
快適で汚染リスクの少ない作業服を選ぶ
作業服は、衛生管理を徹底できることと、作業しやすい快適性を兼ね備えていることが望ましいです。
前述した通り、適切かつ清潔な服装を徹底できていなければ、体毛や汗、ごみなどの異物が混入するリスクが高まります。そのため、適切な頻度で洗濯・交換し、ボタンやポケットのないタイプ・袖口や裾が絞れるタイプなど、異物混入の可能性を減らすデザインを選ぶことが重要です。
しかし、食品事故防止だけを優先すると、快適性が損なわれ、従業員の健康への悪影響や作業効率・生産性の低下を招く恐れがあります。快適な作業環境を提供することは、従業員の作業への意欲を高めるとともに、衛生意識の向上にも役立つので、快適性にも配慮した作業服選びが大切です。
例えば、高温環境でも快適に作業できるようにするためには、アタックベース株式会社の白衣型空調作業服『空調風神服 白衣』がおすすめです。この空調作業服は、作業着内に強力な風を送り込める設計になっており、作業員の快適性を維持して、熱中症予防にも役立ちます。また体毛防止ネットが付いているため、風を循環させても、体毛が落ちてしまうリスクを軽減できるのが特徴です。
食品工場における服装の基本ルールや選び方については、以下の記事でより詳しく解説しています。
空気質を維持し見えないリスクを排除する
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実践するには、空気中の衛生状態を良好に保ち、目に見えないリスクを可能な限り排除することが重要です。
前述の通り、空気中に浮遊する細菌や微細なほこりが食品に付着すると、食中毒や異物混入のリスクが高まります。さらに、適切な温度管理が行われていない場合、食品の劣化や細菌の増殖を招き、食品事故を引き起こすかもしれません。
ここからは、空気質を維持するための具体的な方法をご紹介します。
空気を管理できる業務用空気清浄機を導入する
空気中の目に見えない汚れを除去するには、業務用空気清浄機の導入が効果的です。
食品を扱う空間は、特に衛生状態に細心の注意を払う必要があります。7Sを徹底し、適切な頻度で清掃や消毒を行えば、ある程度は衛生状態を維持できますが、空気中の浮遊菌や微細なほこりまで管理するのは難しいです。
しかし、業務用空気清浄機を導入すれば、目に見えない空気中の菌や微粒子を効率的に除去できるので、衛生環境のさらなる向上が期待できます。
例えばアマノ株式会社の業務用空気清浄機『あまつかぜ』は、特許を取得した電気集じん機能を搭載しており、0.1μmの微粒子を99.9%以上捕集(※)できるのが特徴です。また、高出力の深紫外線ランプを備えており、ウイルスを効果的に抑制できます。
※アマノ株式会社パーティクルサイザーによる測定
殺菌効果のあるランプを導入する
HACCP基準に沿った衛生管理を徹底するためには、殺菌効果を持つランプの活用も有効です。
紫外線には、空気中や食品表面に存在する細菌を死滅させる働きがあり、細菌の付着や増殖を防ぐ効果が期待できます。製造・加工などの工程で衛生レベルを高めるために、殺菌効果のあるランプを導入する事業者は少なくありません。
しかし、食品を扱う工場や施設でランプが破損すると、ガラス片が混入する危険性があります。そのため、導入する際は異物混入を防げる製品の選定が欠かせません。また紫外線が直接人体に当たると、健康被害のリスクがあるので、安全な照射方法や構造が採用されている製品を選ぶことも大切です。
極光電気株式会社の『飛散防止型殺菌ランプFP』は、ランプの外側全面を被覆しているため万一の破損時でもガラスの飛散がなく、安心してご使用いただけます。紫外線の透過効率に優れ、従来品と同等の殺菌線強度を維持しながら、長期間の使用が可能です。さらに、耐薬品性や耐候性にも優れており、食品製造工場、調理器具や医療機器の殺菌など幅広い用途に対応します。
ラインナップは4Wから40Wまでと幅広く、室内空気の殺菌、食品の腐敗防止、調理・医療器具の表面殺菌、水の殺菌など多様な場面で効果を発揮します。安全と衛生を重視する現場に最適な選択肢といえるでしょう。
温度・湿度・照度を感知するセンサーを置いて管理する
食品を保管する冷蔵庫や冷凍庫などに温度・湿度・照度を感知するセンサーを置いて、衛生管理を行うのも一つの方法です。
食品の鮮度を保つためには、温度・湿度・照度の管理が欠かせません。しかし、適切に管理しているつもりでも、誤作動や不具合などで、本来あるべき設定値からずれてしまうことがあります。すると、食品の腐敗や劣化を招き、食品事故のリスクが高まる原因となります。
温度・湿度・照度を感知するセンサーを導入すれば、異常が発生した際に自動で検知して教えてくれるため、食品の腐敗や劣化を防ぐことが可能です。人による確認の手間も省けるので、従業員の負担も軽減されます。全国展開しているドラッグストアでも、冷蔵・冷凍ケースの温度管理にセンサー機器が導入されており、温度管理を本部に集中させることで、精度の向上を実現しています。
サン電子株式会社のおくだけセンサー『ロガー』 は、温度・湿度・照度の他、加速度や磁気(開閉)データも測定できるセンサー機器です。設置場所に置いてパソコンと接続するだけで、必要な環境データを記録・管理できます。有線接続が不要で、すぐに設置できるため、幅広い事業所でも導入しやすいのが特徴です。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の実施は継続的な努力が必要
食の安全を守る衛生管理体制は、すぐに構築できるものではありません。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の手引書に沿って危険要因を把握し、計画を立てた上で、実践と改善を地道に繰り返すことが大切です。また、定期的な衛生教育を実施し、従業員全体の意識も高めましょう。
より効果的な衛生管理を行うには、設備投資を検討するのも一つの方法です。
カナデンでは、ご紹介した製品の他にも、小規模事業者の衛生管理を支援するさまざまな製品を取り扱っています。お悩みや課題に応じたご提案が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。