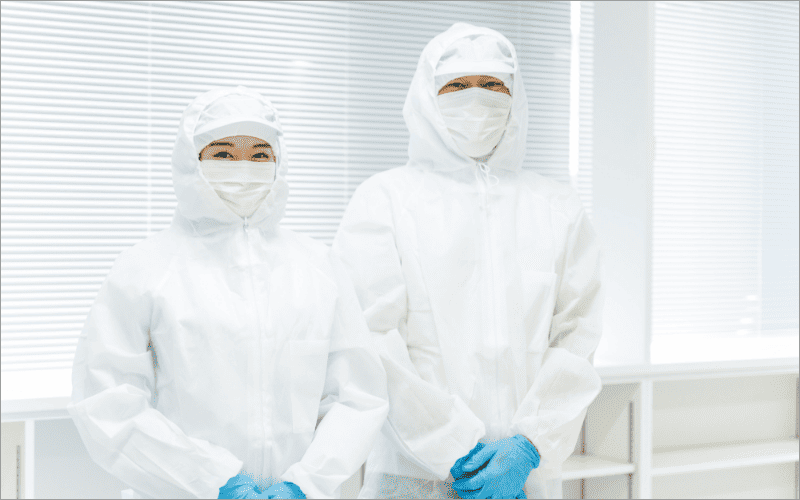食品工場の衛生管理を徹底するには?HACCPや一般衛生管理、実践方法まで徹底解説
公開日:
人の口に直接入る食品を製造する以上、その安全性を確保することは企業の重要な責任です。そのため、食品工場では、他の製造業以上に徹底した衛生管理が求められます。
現在、日本ではHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が全ての食品等事業者に義務付けられていますが、その前提として、一般衛生管理を徹底することも必要不可欠です。
そこで本記事では、食品工場における衛生管理の重要性やHACCPの概要、一般衛生管理のポイント、具体的な実践方法を解説します。食品工場で衛生管理が不十分では、消費者の健康に深刻な影響を及ぼすリスクが高まります。本記事を参考にして、今一度自社の衛生管理体制を見直しましょう。
【この記事で分かること】
- 食品工場で衛生管理が重要な理由
- HACCPの概要
- 一般衛生管理のポイントと具体的な実践方法
なぜ食品工場の衛生管理はこれほど重要なのか?
食品工場における衛生管理は、食品事故を未然に防ぎ、消費者へ安全かつ高品質な食品を届けるために欠かせない取り組みです。
どのような工場でも衛生管理の重要性は指摘されていますが、特に食品工場では、消費者が口にする製品を扱うので、衛生管理が不十分だと食中毒や異物混入といったリスクが高まります。万一食品事故が発生すれば、企業の信頼を失い、場合によっては事業の継続すら困難になる恐れがあるため、十分に対策を取らなくてはなりません。
従来も衛生管理は行われていましたが、2000年に発生した大規模な食中毒事件をきっかけに、2003年に国内で総合衛生管理製造過程承認制度の見直しが進められました(※1)。その後、2018年に食品衛生法が改正され、2020年6月1日からは全ての食品等事業者に、国際基準であるHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました(※2)。
1年の経過措置を経て、2021年6月1日からはHACCPの導入が完全義務化され、食品工場における衛生管理の重要性はこれまで以上に高まっています(※2)。
※1 出典:厚生労働省「HACCP導入普及推進の取組」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000076152.pdf
※2 出典:厚生労働省「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化」https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000662484.pdf
HACCPに沿った衛生管理は事業者の規模によって異なり、本記事で解説する食品工場などが対象の「HACCPに基づく衛生管理」のほかに、小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」があります。小規模事業者向けの衛生管理については、以下の記事をご覧ください。
▶HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは?小規模事業者が抱えるリスクや実践方法も紹介
HACCP(ハサップ)とは?
HACCP(ハサップ)とは、Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析重要管理点)の略称で、国際的な衛生管理の手法を意味します。
ここでいう危害とは、人体に有害な物質や異物、ウイルスなどの混入・増殖によって発生する健康への悪影響のことです。「危害分析」では、原材料の受け入れから最終製品までの工程ごとに起こり得る危害を予測し、管理方法をルール化します。
そして全工程のうち、危害の発生防止やリスク低減につながりやすい特に重要な工程(加熱や冷却)や条件(温度や時間)などを「重要管理点」として、より厳重な管理を行うことも求められます。重要管理点に関しては、継続的な管理・記録が必要です。
従来の衛生管理は、最終製品を抜き取って、細菌試験や異物試験を行っていました。HACCPに沿った衛生管理では、製造工程ごとにリスクを管理することで、食品事故につながる製品の出荷を未然に防ぐことができます。さらに、万一事故が発生した場合でも、原因工程を速やかに特定し、迅速かつ的確に対応を取ることが可能です。
以下の記事ではHACCPの導入メリットや製造ジャンル別の具体的な取り組みについて解説しているので、併せて参考にしてみてください。
▶【ジャンル別】食品製造業におけるHACCPの考え方と解決策
HACCPの土台「一般衛生管理」とは? 押さえるべき3つのポイント
HACCPに沿った衛生管理の実施は義務ですが、その前提として欠かせないのが、どの食品に対しても必ず実施しなければならない「一般衛生管理」です。
一般衛生管理とは、食品を製造したり取り扱ったりする全ての事業者に求められる基本的な衛生管理を指します。HACCPに沿った衛生管理をしても、一般衛生管理が不十分な状態では製品の安全性は確保できないため、一般衛生管理についてもきちんと理解しておかなければなりません。
ここからは、一般衛生管理で押さえるべき3つのポイントを見ていきましょう。
1.作業員の衛生管理:正しい手洗い・服装の徹底

作業員の衛生管理では、正しい手洗いと適切な服装の徹底が必要です。
業務開始時やトイレへ行った後、ゴミなどを触った後、扱う食材が変わるときなどは、正しく手を洗い、細菌やウイルスを洗い流しましょう。
【正しい手洗い手順】
- 流水で手を洗う
- 洗浄剤を手に取る
- 手の平、指の腹面を洗う
- 手の甲、指の背を洗う
- 指の間(側面)、股(付け根)を洗う
- 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う
- 指先を洗う
- 手首を洗う(内側・側面・外側)
- 洗浄剤を十分な流水でよく洗い流す
- 手を拭き、乾燥させる
- アルコールなどで消毒する
(※)
効果的な衛生管理をするには、2〜9の流れを2度繰り返すことが推奨されています。
また、体毛が食品に混入するのを防ぐために、ユニフォームや帽子を正しく身に付けることも欠かせません。細菌や異物の付着を防ぐため、作業着は作業エリア内のみで使用し、着用方法をルール化して全員に周知徹底しましょう。
※出典:厚生労働省「できていますか?衛生的な手洗い」https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/link01-01_leaf02.pdf
作業員の服装に関する具体的なルールや、異物混入リスクの低い作業服の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
2.工場内の衛生管理
一般衛生管理には、工場内の衛生管理も含まれています。
ここからは工場内の衛生管理について、「物品の清掃・消毒」と「空気質の維持」に分けて解説します。
物品の清掃・消毒の徹底
工場の衛生状態を維持するためには、機械や加工・調理器具、布巾など、工場内にある全てのものの清掃・消毒を徹底する必要があります。
その際、清掃や洗浄に使用する道具によって菌の増殖や汚染を防ぐために、清掃箇所や対象物などにあわせて、道具を適切に使い分けましょう。また清掃・洗浄後は消毒を行い、洗い流し切れなかった菌の増殖を防ぐことも大切です。
アルコールや薬品を使った消毒方法の他、電解次亜水やオゾン水などで除菌する方法があります。アルコールでは、ノロウイルスやロタウイルスといった特定のウイルスや細菌の芽胞が懸念される場面では除菌力が十分ではなく、機械へ使用することで引火の危険があるため、オゾン水と電解次亜水を使い分ける必要があります。
安全に衛生環境を維持するのであれば、食品へは電解次亜水、機械へはオゾン水など場面に合わせて使い分けることがより効果的です。
電解次亜水は厚生労働省が「食品添加物殺菌料」として指定するアルカリ性の「次亜塩素酸ナトリウム」を主成分としており、食品の鮮度を保ちつつ安価に、かつ安全に除菌・殺菌することができます。
オゾン水はアルコールのような燃えやすさや材質の変質・変色のリスクがなく、電解次亜水の次亜塩素酸イオンや塩素イオンによる金属腐食の懸念がないため、包丁やまな板、シンク、食器などの調理器具、病院内の医療器具、机、椅子など、さらには精密機器の部品の洗浄にも安心して使用できます。
空気質維持の徹底
工場内の衛生管理では、空気環境の維持も欠かせません。
空気中には微生物やほこりなどの異物が含まれています。そのため、適切な空気質を維持できていないと、食中毒や異物混入などを引き起こすリスクが高まってしまいます。
良好な空気環境を維持するには、通風システムや空調システムを適切に運用し、温度や湿度を管理して、微生物の増殖や食品の劣化を防ぐことが大切です。また、高性能フィルターやUV-Cライトなどを活用し、空気中の微生物や粉じんの拡散を抑えることも、空気の質の維持につながります。
3.食品の衛生管理:温度管理・交差汚染の防止徹底
温度管理と交差汚染防止の徹底は、製造する食品の安全性を確保するために必要不可欠です。
食品の温度管理が適切でなかったり、十分な加熱ができていなかったりすると、食中毒が起こるリスクが高まってしまいます。適切な温度管理を実施するために、温度管理システムの導入や温度記録表の作成・運用などを実施し、食品・工程ごとに適切な温度管理を行うことが大切です。
交差汚染は二次汚染とも呼ばれ、食品に付着している細菌が人や器具を介して、別の食品を汚染することを指します。交差汚染は食中毒の原因の一つなので、原材料保管・調理・運搬など、食品製造における全ての工程で対策を行いましょう。交差汚染を防止するためには、殺菌効果のあるランプの使用や食品ごとの器具の使い分け、一方向の作業動線の確保などの対策が効果的です。
【実践】食品工場の衛生管理を徹底する方法
食品工場の衛生管理を徹底するための具体的な方法の一つに、機器の導入が挙げられます。ここからは、衛生管理を適切に行うためにおすすめの方法をご紹介します。
【作業員の衛生管理】ハンドドライヤー・作業着を導入する
作業員の衛生管理を徹底するためには、ハンドドライヤーや高性能の作業着の導入がおすすめです。
正しい手洗いをしても、共用タオルを使用すると、再び菌が付着してしまう可能性が高いです。ペーパータオルを使用すると衛生的でしょう。
また非接触のハンドドライヤーなら、手を乾燥させる際の接触リスクをなくしつつ、長期的にはコスト削減も期待できます。三菱電機住環境システムズ株式会社のハンドドライヤー『ジェットタオルⓇ』は、使用者への水滴飛散を99.9%(※)防止する「水滴飛散抑制ノズル」を搭載し、菌の飛散を防ぎながら素早く手を乾かせるのが特長です。ヘルスエアー機能を搭載した「衛生強化モデル」なら、設置空間のウイルスや菌を抑制する効果も期待できます。
体毛落下や衛生リスクを低減しつつ、作業員の快適性を確保するには、空調機能付き作業着がおすすめです。アタックベース株式会社の白衣型空調作業服『空調風神服 白衣』は、白衣内に強力な風を循環させるため、高温環境でも快適に作業できます。袖口と裾に体毛防止ネットが付いているので、風によって体毛が落下するのを防げるのが特長です。
※色水を用いて水滴飛散量を確認(三菱電機株式会社調べ)
【工場内の衛生管理】電解次亜水・オゾン水生成機を導入する
前述した通り、食品工場で食品・機器・器具などを消毒する際は、用途に応じてエタノールや電解次亜水・オゾン水などを適切に使い分けます。
例えば、株式会社イシダの電解次亜水生成機『i-CL』を設置すれば、蛇口を開くだけで電解次亜水を使用できます。使用の際に希釈の必要がないため、運用時の手間を省くことができるのが特長です。生成量の異なる2つの機種があり、工場の規模に応じた導入ができます。
また、株式会社フジファインズのオゾン水生成システム『O3MAX Water System』は、水道管に取り付けるタイプの製品です。添加剤を使用せず、水だけで高純度のオゾン水を生成できるので、コストを抑えて運用できます。メンテナンスも不要なため、手間もかかりません。ナノバブル生成システム『MAXナノバブル』を同時に設置すれば、超微細気泡でさらに洗浄力を高めることが可能です。
【工場内の衛生管理】業務用空気清浄機を導入する
工場内の空気の質を維持するには、業務用空気清浄機の導入が効果的です。
アマノ株式会社の業務用空気清浄機『あまつかぜ』は、特許を取得した独自の放電技術「ブラシ放電」で、ウイルスを含めた空気中の0.1μmの微粒子の99.9%(※)を集じんし、清潔な空気の維持をサポートします。電気集じん式の業務用空気清浄機は、フィルターの目詰まりが発生しにくいので、メンテナンスの手間を大幅に軽減することが可能です。また、高出力の深紫外線によって、ウイルスを殺菌する効果も期待できます。
※アマノ株式会社パーティクルサイザーによる測定
【食品の衛生管理】飛散防止型殺菌ランプを導入する
食品の交差汚染防止には、紫外線による殺菌が有効です。そのための設備として殺菌ランプがありますが、通常のランプは破損時にガラス片が飛散するリスクがあるので、導入を躊躇する方もいるかもしれません。
そこでおすすめなのが、飛散防止型の殺菌ランプです。極光電気株式会社の『飛散防止型殺菌ランプFP』は、ランプの外側全面を被膜で覆っているため、万が一ランプが割れても、ガラスが飛び散る心配がありません。被膜には経年劣化しづらく、汚れが付着しにくい素材を使用しているため、長期的に飛散防止効果を発揮する上、メンテナンスの手間も軽減できます。
紫外線を効率よく透過するランプを採用しているので、一般的な殺菌ランプと同等の殺菌効果を維持しながら、安全性と衛生面を両立できるのが特長です。
食品工場での衛生管理ルールを守らせる教育

食品工場で衛生管理を徹底するには、衛生管理の手順や基準をルール化し、それを全作業員に守らせる教育が必要です。
そのためには、以下の取り組みを実施しましょう。
- 衛生管理の目的を周知する
- マニュアルを作成・周知する
- 作業中はチェックシートを付ける
- 衛生管理の記録を付ける
ルールを守らせるためには、内容を伝えるだけでなく、その重要性を理解させることが不可欠です。適切な衛生管理は食品事故の発生リスクを減らし、消費者の安全を守るとともに、企業の信頼や事業継続を支える基盤となることを伝えましょう。
また、ルールは口頭で伝えるだけでなく、マニュアルを作成して、周知徹底することが大切です。特に動画マニュアルは、動作や手順を視覚的に伝えられるため、内容が伝わりやすいです。マニュアルは、いつでも誰もが確認できる状態にしておきましょう。
作業漏れやミスを防ぐためには、衛生管理の作業項目をまとめたチェックシートを活用し、日々の業務中に確認します。加えて、温度管理などの重要項目の記録を残すことで、万が一食品事故が発生した場合でもすぐに適切な対応を取ることが可能です。
徹底した衛生管理と適切な設備投資で食の安全を守る
食品工場における衛生管理は、消費者の安全を守るために必要不可欠な取り組みです。万が一食品事故が発生すれば、自社の信用が大きく損なわれ、経営に大きな打撃を与える可能性も高くなります。食の安全を守り、自社を成長させるためにも、日常的に適切な衛生管理を行いましょう。
衛生管理にはさまざまな方法がありますが、より精度の高い管理を行うには、設備投資を行うことも重要です。自社の衛生管理体制を確認し、課題を洗い出し、必要に応じた設備の導入を検討してみてください。
株式会社カナデンでは、本記事でご紹介した製品をはじめ、食品工場の衛生管理をサポートするさまざまな機器を取り扱っています。設備投資による衛生管理の強化をご検討の際は、ぜひカナデンまでお気軽にご相談ください。