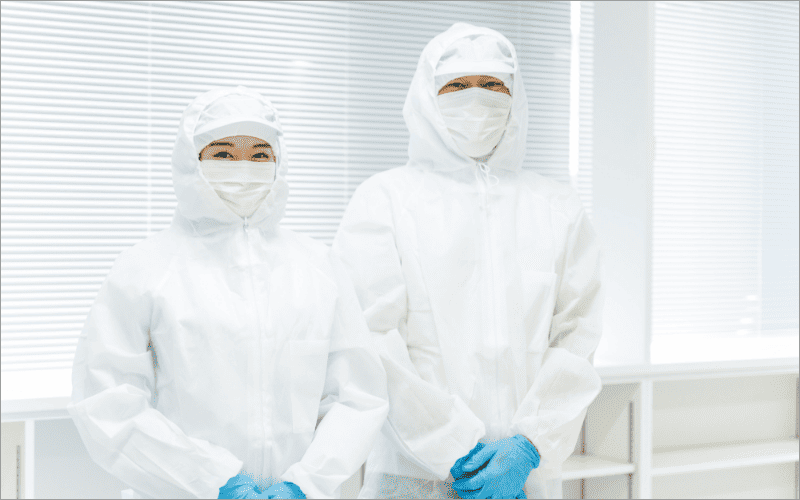工場の安全衛生管理とは?押さえておきたい法律や具体策を解説!
公開日:
安全衛生管理とは、従業員の安全・健康を確保し、事故や健康被害のリスクを軽減するための取り組みのことです。さまざまなリスクが潜んでいる上、過酷な労働環境になりやすい工場では、安全衛生管理対策が欠かせません。
そこで本記事では、工場で安全衛生管理対策が重要な理由や関連する法律、工場が取り組むべき具体的な衛生管理対策などを解説します。安全衛生管理を怠ると、従業員の安全・健康を損なうだけでなく、自社の成長を妨げる恐れもあります。
「安全衛生管理で何をすればいいか分からない」という方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
【この記事で分かること】
- 工場で安全衛生管理が重要な理由と目的
- 安全衛生管理に関する法律
- 工場で気を付けたい安全衛生管理対策に関わる健康被害
- 安全衛生管理の具体的な対策例
特に食品を扱う工場の衛生管理については、国際的な基準であるHACCP(ハサップ)への対応が不可欠です。詳しくは以下の記事で解説しています。
▶食品工場の衛生管理を徹底するには?HACCPや一般衛生管理、実践方法まで徹底解説
工場における安全衛生管理とは?その重要性と目的
工場における安全衛生管理とは、工場内で作業に関わる全ての人の安全と健康を守り、業務中に起こり得る事故や健康被害を未然に防ぐために、事業者が主体となって行う一連の取り組みを指します。具体的な取り組みの例は、以下の通りです。
- 労働災害防止対策の実施
- 職業性疾病発生の未然防止
- 健康維持および増進施策の推進
- 快適かつ効率的な作業環境の整備
安全衛生管理の大きな目的の一つは、従業員の命と健康を守ることです。法律でも、原則全ての事業者に対して適切な安全衛生管理の実施が義務付けられており、企業が社会的責任を果たすためにも欠かせません。
万が一、労働災害が発生すれば、従業員やその家族に深刻な影響を与えるだけでなく、生産力の低下や損害賠償など、企業の事業運営に大きな支障を来す恐れがあります。
なお、特定の業種で一定規模以上の労働者を常時使用する事業場には、安全や健康を管理する担当者の選任が法律で義務付けられています。
加工業を含む製造業などの業種では、常時10人以上50人未満の労働者がいる場合は安全衛生推進者、50人以上の場合は安全管理者および衛生管理者を選任しなければなりません(※1)(※2)(※3)。その他の業種でも、10人以上50人未満の場合は衛生推進者の選任が必要です(※1)。
※1 出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo31_1.html
※2 出典:厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html
※3 出典:厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html
工場の安全衛生管理で押さえておきたい「労働安全衛生法」とは?
工場の安全衛生管理について考える際に、まず押さえておかなければならないのは「労働安全衛生法」です。
この法律では、以下のような規定が定められています。
- 事業者の責務
- 労働者の遵守事項
- 安全管理体制の構築
- 安全衛生教育の実施
- 労働災害防止計画の策定
労働安全衛生法において「労働者」とは、職種に関わらず、会社や事務所、工場などで働き、賃金を受け取っている人です。また「事業者」は、事業を経営し、労働者を雇っている人を指します。
労働安全衛生法の規制に違反すると、行政処分や刑事罰の対象となることがあります。社会的信用の失墜に加え、損害賠償が発生するケースもあり、企業が被るダメージは大きいです。
労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境を作ることを目的に制定されました。簡単にまとめると、労働災害を防ぐことが、この法律の目的です。
この目的を達成するために、以下のような取り組みを行うことが求められます。
- 危険防止に関する基準の策定:業務に伴う健康被害を未然に防ぐため、労働者の健康リスクを把握し、防止措置を講じるために健康診断を行う
- 権限・責任・役割の明確化:安全管理者や安全衛生管理者、産業医など必要な担当者を選任する
- 自主的安全衛生活動の推進:労働者の安全と健康を促進するために、職場の快適性を向上させるための取り組みを推進する
労働安全衛生法が設立された背景
1947年に新憲法が制定された際、労働基準法が整備され、その中の第5章で、安全衛生に関する14条の規定(第42条から第55条まで)が盛り込まれました(※1)。
それ以降、この規定を基にして関連規則が追加されていきますが、戦前に労働安全衛生に関する規則が設けられていたのは労働災害が発生しやすい一部の業種のみでした。
しかし、1950年代中盤から高度経済成長期に入ると、大規模工事の増加や生産技術の急速な進歩によって、労働環境は目まぐるしく変化します。その結果、さまざまな業種で労働災害が多発し、1960年代には労働災害による年間死亡者数が6,000人を超える事態となりました(※2)。
この状況を受け、1969年に労働省と専門家による法整備の検討が開始され、1972年に現行の労働安全衛生法が施行されました(※1)(※3)。施行後、1970年代中盤には死亡者数が3,000人程度まで減少し、2023年には1,000人未満となっています(※2)。
※1 出典:一般社団法人 安全衛生マネジメント協会「労働安全衛生法とは」https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen.html
※2 出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「図1 労働災害による死傷者数、死亡者数 (1965年~2023年)」https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/pdf/g0801.pdf
※3 出典:厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1
労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則とは?
労働安全衛生法には、さまざまな規制が定められていますが、その規制に沿った詳細な取り決めや指針は、内閣が定める「労働安全衛生法施行令」や、厚生労働大臣が定める「労働安全衛生規則」に委ねられています。
労働安全衛生法施行令は「政令」に該当します。法律である「労働安全衛生法」の原則を規定するものです。また労働安全衛生規則は、各大臣によって定められる「省令」に該当し、政令の内容を具体的に規定したものです。
政令・省令は法律に基づいて具体化する下位法令であり、いずれも法的拘束力の大きさに関わらず、遵守しなければならない法令であることを理解しておきましょう。
工場で気を付けたい安全衛生管理対策に関わる健康被害

工場の作業環境には、従業員の健康に影響を及ぼすさまざまなリスクが潜んでいます。ここからは代表的な物をご紹介します。
化学物質・粉じんによる健康被害
工場では、化学物質・粉じんなどが従業員の健康被害につながることがあります。化学物質は皮膚炎や呼吸器障害、長期的にはがんのリスクを高めることがあります。そのため、ラベル表示やSDS(安全データシート)の確認、保護具の着用、局所排気装置の導入などが欠かせません。
粉じんについては、溶接ヒュームや石綿ばく露によるじん肺やぜん息が懸念され、適切な換気やマスク着用に加え、石綿対策は法的に義務化されています。制度や統計に基づいた対策を講じることが、健康被害防止の要です。
暑熱による健康被害
高温多湿の工場環境では、熱中症のリスクが特に高まります。症状は軽度のめまいや脱力感から始まり、進行すると頭痛、吐き気、意識障害など命に関わる深刻な状態に至ることもあります。
予防のためには、厚労省の推奨するリスクアセスメントやWBGT指数の測定を活用し、休憩場所や冷房設備の整備を徹底することが重要です。また、教育・訓練を通じて従業員に熱中症の初期症状や対応を周知する取り組みも有効です。
厚生労働省では「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」などの啓発活動も展開されており、暑熱順化や日常的な健康管理の徹底が求められています。企業が組織的に暑熱対策を進めることは、従業員の命を守り、生産性を維持するために不可欠です。
※出典:厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
工場の暑熱対策については以下の記事でも詳しく解説しています。場所別の対策方法や、従業員個人でできる対策なども紹介しているのでぜひご一読ください。
▶ 工場の熱中症対策で企業ができることは?場所別・個人でできる対策方法をご紹介
工場が取り組むべき具体的な安全衛生管理対策と実践例
工場での労働災害や健康被害を未然に防ぐためには、衛生管理対策の徹底が重要です。では、具体的にどのような取り組みを行えば、職場の衛生環境を改善し、労働災害を防げるのでしょうか。
ここからは、工場が取り組むべき具体的な衛生管理対策とその実践例を紹介します。
従業員の意識向上
安全衛生管理を適切に行うためには、まず従業員一人ひとりの意識を向上させることが欠かせません。
工場には正社員だけでなく、派遣社員やパート・アルバイトなど、多様な雇用形態の人が働いています。新人からベテランまで経験もさまざまで、作業に対する意識にも差があるでしょう。労働災害をなくすには、雇用形態や経験年数に関係なく、全員が安全衛生を意識することが重要です。
そのためには、まずトップが先頭に立ち、全社を挙げて安全衛生管理に取り組む必要があります。経営者や工場長が方針を示し、トップダウンで施策を推進しましょう。また、朝礼での確認事項の唱和や、掲示板でのヒヤリ・ハット事例の共有など、日常的に意識を喚起する取り組みも、安全意識の向上に効果的です。
従業員の健康管理
労働災害を防ぐためには、安全への意識だけでなく、従業員の健康管理も欠かせません。健康状態が悪ければ集中力が低下し、注意散漫となって事故のリスクが高まります。
適切な健康管理を行うためには、定期健康診断を必ず実施しましょう。労働安全衛生法では、1年以内ごとに1度の定期健康診断が義務付けられています(※)。著しく高温・寒冷な場所で作業する従業員や有害放射線にさらされる作業員など、特定の作業に従事する場合は、6カ月以内ごとに1回の特定業務従事者健康診断も実施しなければなりません(※)。
また高年齢労働者の増加に伴い、高齢者の労働災害発生率は上昇傾向にあります。身体機能や記憶力の低下に配慮し、適切な人員配置や業務内容の調整を行いましょう。加えて、経験が浅い若年者に対しては、安全衛生教育の徹底や、業務意欲の向上を目的とした積極的なコミュニケーションが重要です。
高温環境になりがちな工場では、熱中症のリスクも高まります。従業員の健康を守りながら、生産性を向上するには、快適な作業環境を整備するために作業服を見直すことも一つの方法です。
例えば、白衣型空調作業服『空調風神服 白衣』は、白衣内に強力な風を循環させることで、過酷な作業環境でも快適さを向上できます。体毛防止ネットが付いていて、白衣の密閉性も高いため、異物混入を防ぎながら従業員の健康維持にも配慮できるのが特徴です。
※出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
従業員の意見を聞く
安全衛生管理を徹底するためには、意識的に従業員の意見を聞く姿勢を持つことも大切です。
日常に潜む労働災害のリスクを軽減するには、年齢や経験、雇用形態に関わらず、誰もが意見を言いやすい風通しの良い職場環境を整えます。管理職から積極的に声を掛けたり、定期的な面談を行ったりして、意見を出しやすい雰囲気作りを意識しましょう。
また、目安箱の設置や改善提案制度の導入など、現場の声を吸い上げる仕組みを整えることも効果的です。集めた意見を参考に、安全衛生管理の改善に生かしましょう。
安全衛生教育とトレーニングの継続
継続的に安全衛生教育とトレーニングを実施することも、工場の安全衛生管理には欠かせません。
雇用時だけでなく、全ての従業員に対して、定期的な教育・トレーニングを実施します。作業の方法や注意事項を伝える際は、教育の目的に応じて、座学・動画視聴・資料配布など、適切な方法を選ぶことが大切です。事例を交えて具体的に説明し、「なぜ必要なのか」という理由も併せて伝えましょう。
KYT(危険予知訓練)も効果的な教育手法の一つです。KYTでは、作業や現場の状況を示したイラストシートから危険を見つけ出し、その要因や発生し得る事故について話し合い、危険要因をなくすための行動目標を策定します。定期的に実施することで、全従業員が注意すべきポイントを理解し、意識を持って作業に取り組むことが可能です。
衛生環境を保つためには、作業環境の清潔維持と感染症予防も欠かせません。例えば、ハンドドライヤー『ジェットタオルⓇ』を導入すれば、共用タオルによる繰り返しの手拭きをなくせるので、従業員の衛生向上につながります。同製品の「衛生強化モデル」には「ヘルスエアーⓇ機能」が搭載されており、設置周辺の空気清浄も行えるため、作業環境の衛生管理にも貢献します。
5S活動による職場環境の改善
5S活動とは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った取り組みのことです。以下のように5S活動を行うことで、工場内の環境が改善し、精度の高い安全衛生管理が行えるようになります。
- 整理:必要なものと不要なものを仕分けし、不要なものを処分する
- 整頓:物の置き場所や収納方法を決めて表示し、必要なものをすぐに取り出せるようにする
- 清掃:定期的に清掃をし、ゴミや汚れがない状態にする
- 清潔:整理・整頓・清掃を行い、清潔な状態を維持する
- しつけ:ルール通りに習慣化できるように教育する
5S活動を適切に行うには、作業中や前後の習慣として取り入れることが重要です。これにより、作業効率が向上し、工場全体の生産性も高まります。また整理整頓を行うことで転倒などリスクを軽減し、適切な清掃を行うことで機械や工具のメンテナンス不足による事故防止にも効果が期待できます。
食品を扱う現場では、食中毒のリスクを軽減するために、5Sに「洗浄・殺菌」を加えた「7S活動」を行うことが望ましいです。
この7Sは、国際的な衛生管理基準であるHACCP(ハサップ)においても重要な実践項目とされています。小規模事業者向けのHACCPや7Sを徹底する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
▶HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは?小規模事業者が抱えるリスクや実践方法も紹介
リスク評価と管理の徹底
危険源を洗い出してリスク評価を行い、それを取り除くための適切な管理を行うことも、安全衛生管理には重要です。
危険源はリスクが発生する要因となるものを指し、この危険源に人が近づくことで、災害が起こる可能性が高まります。労働災害を防ぐためには、現場に発生する危険源を洗い出し、どのような作業と関連するかを明確にした上で、リスクの高さを評価する必要があります。その上で、どのような対策を講じるかを検討し、リスクごとに管理を行うことが大切です。
この一連の取り組みに効果的な方法としては、前述したKYTの他、安全パトロール、リスクアセスメントも有効です。安全パトロールは責任者などが定期的に現場を巡視・点検し、リスクにつながる箇所がないかを確認する取り組みを指します。リスクアセスメントは、危険源の特定からリスクの見積もり、リスク低減策の策定までの一連のプロセスのことです。
事故報告と再発防止策の徹底
工場の安全衛生管理対策として、事故報告と再発防止策を徹底することも大切です。
安全衛生管理対策を実施していても、事故が発生する可能性はゼロではありません。万が一事故が起きた場合、最も重要なのは再発を防ぐことです。事故の規模に関わらず、発生後は速やかに原因を調査し、再発防止策を検討しましょう。
また適切な対応が取れるよう、事故発生時の対応フローを事前に明確化しておくことが重要です。行政への報告・届出のための記録作成も欠かせません。これらの記録は、再発防止や従業員の意識向上にも役立ちます。
事故報告の重要性は、「ハインリッヒの法則」によっても裏付けられています。これは“同じ人間が起こした330件の災害のうち、1件は重い災害(死亡や手足の切断等の大事故のみではない。)があったとすると、29回の軽傷(応急手当だけですむかすり傷)、傷害のない事故(傷害や物損の可能性があるもの)を300回起こしている。”というものです(※)。
この法則に基づくと、「300件のヒヤリ・ハットには、29件の軽微な事故と1件の重大事故が存在する」ということになります。事故防止のためには、ヒヤリ・ハットゼロを目指し、ヒヤリ・ハットの情報収集と記録、そして改善策の実施も併せて行いましょう。
※出典:職場のあんぜんサイト「ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo24_1.html
持続的な改善(PDCAサイクル)
従業員が安全かつ健康に働ける工場を維持するには、安全衛生管理対策を継続的に改善する必要があります。
安全衛生管理対策は一度講じて終わりではありません。実施した対策に課題や問題が出てくるケースもある上、作業環境や使用する機器が変われば、必要な対策は変わってきます。
対策は目標に沿って実行した後、その効果を評価し、定期的に見直して改善します。この流れを回すのがPDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)です。PDCAを継続的に回すことで、現状に即した安全衛生管理対策を維持し、事故防止につなげることができます。
衛生管理レベルを高めるための設備投資
工場の安全衛生管理を適切に行うためには、衛生管理レベルを高めるために設備投資を行うことも検討しましょう。
人による安全衛生管理対策は重要ですが、それだけでは労働災害の防止や作業環境の衛生維持に限界があります。そこでおすすめなのが、設備の導入です。
例えば、空気中の細菌やウイルスを不活化させる殺菌ランプを設置すれば、食中毒のリスク軽減につながります。ランプは破損のリスクがありますが、ランプの表面を被膜で覆った『飛散防止型殺菌ランプFP』なら、万が一破損しても、ガラスが混入する恐れがない上、従業員のけがを防ぐことが可能です。
また、業務用空気清浄機を導入すると、広い工場空間の空気を短時間で効率的に清浄できます。例えばアマノ株式会社の業務用空気清浄機『あまつかぜ』は、電気の力で0.1μmの微粒子を99.9%捕集し、深紫外線でウイルスを確実に除菌する性能を備えています(※)。
また粉じん対策として、集じん機を導入することでより健康被害のリスクを低減できます。例えばSDG株式会社のコンパクト集塵機『ダストレーサ』は低騒音で高性能ターボ型送風機を備えた製品です。送風機メーカならではのろ過面積の広さや集じん効率の高さ、目詰まりの少なさからコストパフォーマンスに優れた粉じん対策性能を備えています。
※:アマノ株式会社パーティクルサイザーによる測定
安全衛生管理を徹底しステークホルダーの信頼を獲得しましょう
安全衛生管理を怠ると、従業員の安全や健康を損なうだけでなく、自社への信頼低下にもつながります。従業員を守り、安定した経営を続けるためには、安全衛生管理を徹底し、労働災害や健康被害を未然に防ぐことが不可欠です。まずは自社の現状を把握し、必要に応じて適切な対策を立て、安全衛生管理対策を徹底しましょう。
人の手による安全衛生管理と併せて、設備投資による対策も有効です。
株式会社カナデンでは、ご紹介した製品以外にも、安全対策に役立つさまざまな製品・システムを扱っています。自社の安全衛生管理に課題を抱えている方は、お気軽にカナデンにお問い合わせください。