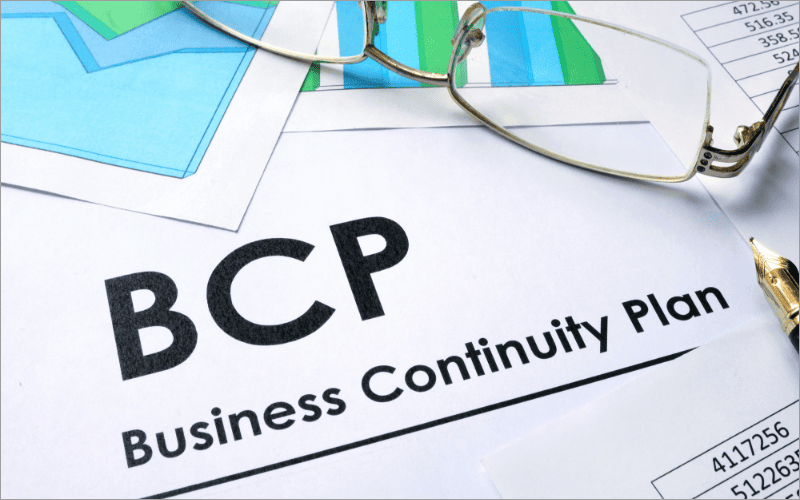企業が取り組むべき災害対策とは?企業防災の基本的な考え方・具体的な進め方について解説
公開日:

地震や台風といった自然災害は、いつ発生するか予測できません。企業においても、こうした災害への対策を講じておくことは非常に重要な取り組みといえます。
この記事では、企業が災害対策に取り組む目的や、企業防災の義務とメリット、具体的な進め方についてわかりやすく解説しています。とくに製造業(工場)に求められる災害対策や、企業防災に役立つ設備の例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
企業が災害対策に取り組む目的
企業が災害対策に取り組む目的として、「防災に取り組むため」「事業継続を実現するため」という2点が挙げられます。まずは、それぞれの目的を明確に理解しておくことが大切です。
防災に取り組むため
災害対策への取り組みが企業に求められる理由の1つは、従業員をはじめとする関係者の安全を確保し、被害を最小限にとどめる必要があるからです。大地震などの災害が発生した場合、従業員の生命を守るとともに、安否を迅速に確認しなければなりません。これは従業員を雇っている企業が必ず履行するべき義務であり、業種を問わず必須の取り組みといえます。従業員が安心して就業できる環境を整えるためにも、企業防災に注力する必要があるでしょう。
事業継続を実現するため
もう1つの重要な理由として、事業継続の実現が挙げられます。大規模な災害に見舞われた場合、建物や設備・機器の損壊によって平時と同じように業務を遂行できない状況に陥りかねません。また、必要な情報が収集できなかったり、連絡を取り合えなかったりすれば、誤った判断を下してしまうおそれもあります。こうした事態を未然に防ぐためにも、災害対策をあらかじめ講じておくことは企業にとって重要な課題です。企業などの組織が不測の事態に直面した際には、事業が中断するのを防いだり、仮に中断してもできるだけ短期間で復旧を目指したりする必要があります。このような、事業継続を実現するための計画のことを「事業継続計画(BCP: Business Continuity Plan)」といいます。
事業継続計画(BCP)の策定は、災害のほか感染症のまん延やテロといった緊急事態に備え、重要度の高い業務の継続・再開を目指すための取り組みです。自社にとって重要な事業が停滞・廃止に追い込まれないようにするためにも、実効性のある計画を立てておかなければなりません。
▶関連記事:BCP(事業継続計画)とは?BCMとの違いや策定のメリット・手順を解説
企業防災の義務とメリット

災害対策は企業にとって義務であると同時に、事業上のメリットを得られる取り組みでもあります。企業防災の義務とメリットの両面を確認しておきましょう。
法的義務の履行
あらゆる企業には、災害対策を講じる義務が課されています。関連する主な法令は次のとおりです。
- 労働契約法(災害発生時を含む安全配慮義務)
- 建築基準法(防火設備の設置、耐震性の確保、防災管理者の選任など)
- 消防法(防災体制の整備、防災訓練の実施、防災マニュアルの作成など)
事業者は適切な災害対策を講じ、これらの義務を履行しなければなりません。企業防災は事業者ごとの判断に委ねられている取り組みではなく、法的義務である点を十分に理解しておくことが重要です。
各種条例への対応
前述の各種法令に加え、自治体ごとに企業防災に関連する条例が定められているケースも少なくありません。一例として、東京都が定めている「帰宅困難者対策条例」では災害発生時に従業員が一斉に帰宅することを抑制することや、従業員の3日分の食料や飲料水等を備蓄することが企業の努力義務とされています。事業所の所在地における各種条例についても入念に確認し、しかるべき対策を講じておく必要があるでしょう。
対外的な信頼確保
災害対策は企業にとって義務もしくは努力義務であると同時に、事業上のメリットを得られる取り組みともいえます。災害発生時に備えて安全確保に取り組み、事業継続に向けた対策を講じていること自体が、ステークホルダーの信頼獲得につながるからです。取引先や顧客にとって、「万が一の事態が発生しても商品やサービスを安定供給できる」ことは、企業に対する信頼を大きく左右する要素の1つです。対外的な信頼を向上させる意味においても、企業防災は大きな意義のある取り組みといえます。
企業防災の具体的な進め方

ここからは、企業防災の具体的な進め方について解説していきます。災害発生時に不備が発覚することのないよう、次の手順に沿って対策を進めていきましょう。
起こり得るリスクを把握する
第一に取り組むべきことは、起こり得るリスクの把握です。事業所の立地や事業内容・業務の特性を整理し、災害発生時に起こり得る事態を予測します。また、過去の災害発生状況やハザードマップなども参照し、どのような被害が想定されるのかをシミュレーションしましょう。やみくもに対策を講じるのではなく、起こり得るリスクと想定される被害の規模を踏まえて災害対策の方針を決めることが重要です。
防災計画を立てる
洗い出したリスクに対して、必要とされる対策を検討していきます。災害発生時に指揮をとる責任者や連絡手段、安否確認の方法、避難経路などを具体的に詰めておくことが大切です。
防災計画では、発生し得る災害別に対処方法を決めておく必要があります。地震や浸水、土砂災害など、災害ごとに事業所が受ける可能性のある被害を想定し、対策を検討しましょう。
計画に沿って準備を整える
防災計画を実行する上で必要な準備を整えていきます。防災グッズの準備をはじめ、設備・機器などの固定、データの分散化といった措置を1つずつ講じましょう。現状整っていない防災設備に関しては、新たに導入することも視野に入れて検討する必要があります。優先順位を見極め、必要性の高いものから計画的に準備を進めていくことが重要です。
【備蓄品・防災設備の例】
防災訓練を実施する
災害対策の計画を立てただけでは実効性は期待できません。計画に沿って定期的に訓練を実施し、実践を通して災害発生時の動きを確認しておくことが非常に重要です。
たとえば、計画上では指示系統が不備なく定められているとしましょう。実際に行動に移してみると「誰が」「どのような手段で」「どのタイミングで」「誰に対して」指示するのか、曖昧な点が残っていることも十分に考えられます。災害発生時にこうした混乱を招かないためにも、定期的に訓練を実施することには大きな意義があるのです。
計画を適宜更新する
防災訓練を通じて浮上した課題を検証し、計画の改善を図っていきます。このプロセスを繰り返すことが、実態に即した防災計画の策定につながるでしょう。
また、組織変更や人事異動が行われた際には、防災計画も連動して更新しなければなりません。実在しない古い部署名が記載されたままになっていたり、組織変更前の責任者・担当者が記載された状態になっていたりすることのないよう、計画を適宜更新していくことが重要です。
▶関連記事:【令和7年度】非常用電源の導入時に使える補助金とは?補助基準額や適用条件を解説
製造業(工場)に求められる災害対策

災害対策を講じる際には、業種ごとの特性を考慮する必要があります。とくに製造業に関しては、工場が被災して稼働を停止せざるを得ない状況に陥った場合、事業の存続そのものにかかわる重大なダメージを受けることにもなりかねません。製造業(工場)に求められる災害対策を確認しておきましょう。
▶関連記事:製造業に求められるBCP(事業継続計画)とは?策定の流れを事例とともに紹介
経営資源の分散化
経営資源の分散化を図ることは、災害対策を講じる上で非常に重要なポイントです。資源や部品の調達先をはじめ、在庫品の倉庫などを物理的に離れた場所に分散させておくのが望ましいでしょう。こうした対策を講じることで、ある地域が被災した場合に別の地域から調達を継続できたり、被害に遭っていない地域の倉庫から出庫できたりするからです。経営資源が一箇所に集中することのないよう、できる限り分散化を進めましょう。
代替となる生産拠点の確保
生産拠点に関しても複数確保しておくのが理想です。自社に別拠点がある場合は、被災時に活用できるよう準備を進めておくことをおすすめします。自社に複数の生産拠点がない場合は、協定関係にある他社の製造拠点を相互に活用し合えるよう交渉しておくのが望ましいでしょう。大災害が発生した際に、生産が完全にストップすることのないよう対策を講じておくことが重要です。
代替となる生産設備の確保
生産設備を多用途化していくのも有効な対策です。現状の設備をメインの製造工程以外にも活用できるようにすることで、万が一他拠点が被災した場合に代替手段として運用できます。自社で対応するのが難しいようなら、他社に業務を依頼できる体制を確保しておく必要があるでしょう。現状の製造工程が損傷・損壊したとしても、重要度の高い製品については生産を継続できる体制づくりを進めておくことで、より災害に強い生産体制を構築できます。
企業防災に役立つ設備の例
企業防災に役立つ設備の例を紹介します。災害発生時に想定される事態と必要な対策、各設備が活躍するシーンをまとめていますので、防災設備を選定する際に役立ててください。
例1:非常用自家発電設備
商用電源が停止した際の対策も、企業防災において重要な検討事項の1つです。重要度の高い業務を継続するために必要な電力を確保しておくことによって、事業が完全に停止するのを防げます。
非常用自家発電設備には、ガスタービン発電機やディーゼル発電機のほか、水素発電システムなどがあります。自社が必要とする電力量や稼働時間に応じて、適した自家発電設備を選ぶことが大切です。
▶関連記事:【令和7年度】非常用電源の導入時に使える補助金とは?補助基準額や適用条件を解説
例2:落雷現象の回避
落雷は設備や機器の不具合・故障の原因となります。落雷の被害に遭った場合の対応策を検討しておくことも大切ですが、そもそも落雷を回避するための仕組みを構築しておくことも重要な対策といえるでしょう。
「dinnteco-100plus」は、落雷現象を発生させない性能を備えた新型避雷針です。従来の避雷針は雷を「誘導して落とす」仕組みだったのに対して、落雷現象そのものを防ぐ点が大きく異なります。直撃雷サージ(=雷を避雷針に落とすことによって生じる大電流が電子機器や電気設備を破損させる)被害を防ぎたい事業者様におすすめです。
企業の災害対策に関するよくある質問
企業の災害対策に関して、よくある質問をQ&Aにまとめました。
企業防災は義務ですか?
企業防災に必要とされる取り組みは、労働契約法(安全配慮義務)、建築基準法、消防法にそれぞれ定められています。各法令に則った対策を講じることは、あらゆる企業が履行するべき義務です。また、自治体によっては災害に備えた対策や災害発生時の対応について、独自に条例を定めている場合もあります。こうした法令や条例を遵守した組織体制を構築することは、企業としての信頼を損なわないためにも非常に重要な取り組みです。
企業の震災対策とは具体的に何をすればいいのですか?
企業に求められる震災対策として、次の例が挙げられます。
- 機械や設備の転倒防止
- 物品の落下防止
- 避難経路の確保
- 停電への対応
- 重要データの分散管理
- 備蓄品の確保
など
講じるべき対策は、業種や事業内容、稼働している設備機器によって異なります。自社の実態に即した防災計画を立て、定期的な訓練を通じて改善を繰り返していくことが実効性のある震災対策につながるでしょう。
災害対策は企業にとって必須の取り組み
大規模な災害が発生する時期を予測することは不可能です。緊急事態に備えて必要な対策を講じることは、従業員の生命と事業を守っていく上で企業に課された社会的責任といえるでしょう。今回紹介した企業防災の進め方や災害対策の例を参考に、自社の防災計画をあらためて見直してみてはいかがでしょうか。
カナデンでは、万一の災害時にも事業を止めないための「具体的な対策」をご提案しています。従業員の安全確保と事業継続を実現するために、今できることを一緒に考えてみませんか?ささいなご相談でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。