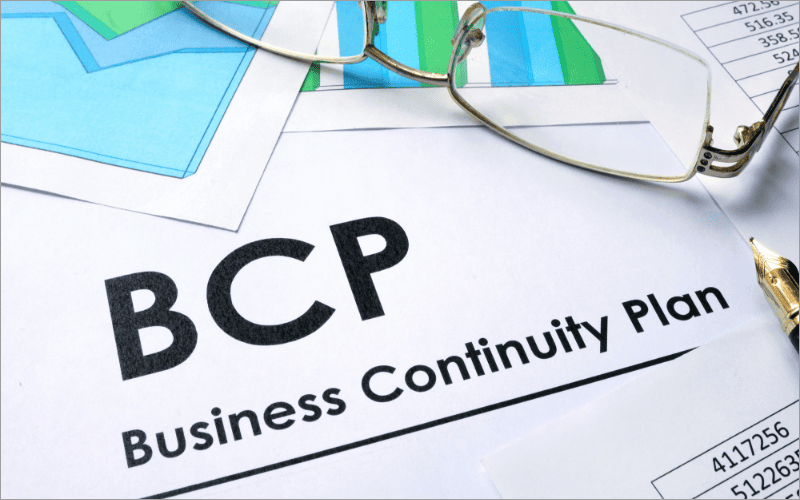介護事業所のBCP(事業継続計画)とは? 義務化された背景と策定時の注意点、運用上の課題を解説
公開日:

2024年4月より、すべての介護事業所においてBCP(事業継続計画)の策定が義務づけられています。現状定めているBCPが適切なものになっているか、どのように改善を図ればよいのか気になっている介護事業者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、介護事業所にてBCPが義務化された背景や策定するメリット、策定時のポイントをわかりやすく解説しています。策定後のBCPを適切に運用していく上で課題となりやすい点もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
介護事業所のBCP策定義務化とは
はじめに、介護事業所のBCP策定義務化について押さえておきたい知識を整理しておきましょう。
そもそもBCPとは
BCP(Business Continuity Plan)とは、事業継続計画のことです。自然災害や感染症のまん延など、緊急事態が発生した際に重要な事業を中断させることなく継続したり、短期間で復旧させたりするための計画のことを指します。
不測の事態に直面しても事業を継続できるよう対策を講じることは、全業種に共通する課題です。ただし、あらゆる業種でBCP策定が義務づけられているわけではありません。一般的にBCPは事業者ごとの判断で策定すべきものであり、あくまでも推奨されている取り組みの1つです。一方、介護業に関してはすべての事業所にBCP策定が義務づけられている点が他業種と異なります。
▶BCP(事業継続計画)とは? BCMとの違いや策定のメリット・手順を解説
介護事業所でのBCP策定が義務化された背景
介護事業所でのBCP策定義務化には、自然災害の増加と感染症の流行に直面したことが大きく関わっています。介護事業者がサービスを中断せざるを得なくなったり、施設の運営を継続できない状況に陥ったりした場合、重大な影響をもたらすことにもなりかねません。こうしたリスクが高まっていることを受けて2021年4月よりBCP策定が義務化され、3年間の経過措置期間を経て2024年4月より全面義務化となりました。
BCP未策定の場合は基本報酬減算の対象となる
前述のとおり、すでに介護事業所のBCP策定は義務となっています。したがって、BCP未策定の事業者に関しては基本報酬減額の対象となる点に注意が必要です。具体的には、施設系・居住系サービスに関しては所定単位数の3%、その他のサービスに関しては所定単位数の1%がそれぞれ減額されます。
なお、経過措置期間は2024年3月末に終了しているため、現在はあらゆる種類の介護事業所が義務化の対象となっています。努力義務ではない点に注意しましょう。
介護事業所でのBCP策定メリット
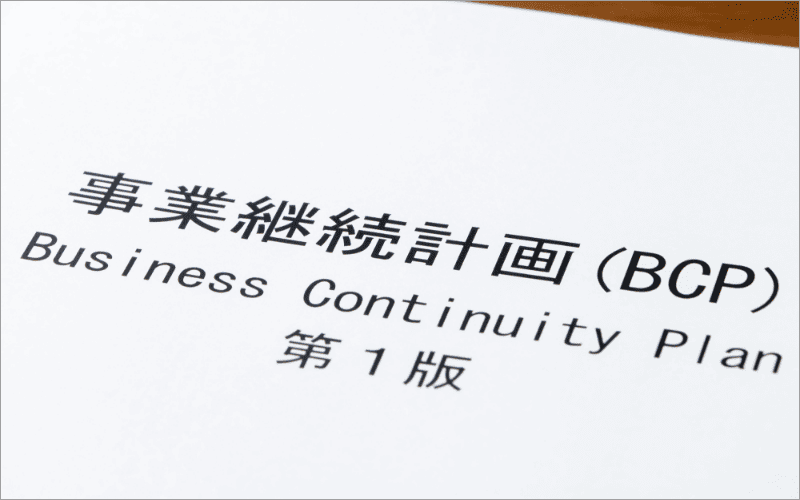
BCP策定は介護事業所に課された義務とはいえ、策定することによって得られるメリットも数多くあります。具体的なメリットとして挙げられるのは次の5点です。
1. 利用者および職員の生命を守れる可能性が高まる
BCP策定を通じて想定されるリスクに備えられるため、有事の際に適切な行動をとりやすくなります。利用者および職員の生命を守るという、介護事業所にとって非常に重要な責務を果たせる可能性が高まるでしょう。結果として利用者はより安心してサービスを利用できます。職員にとっても、勤務先が有事を想定した対策を講じていることは大きな安心材料となるはずです。
2. 事業の存続と早期復旧に寄与する
不測の事態に見舞われた際に経営が受けるダメージを最小限に抑えつつ、施設を維持できる可能性が高まります。災害や感染症のまん延といった緊急事態を想定して対策を講じられることに加え、万が一被害に遭った際にも早期復旧を実現しやすくなるからです。場当たり的な対応ではなく、計画にもとづいて適切に行動できるようにしておくことは、いざという時に対応を誤らないためにも重要なポイントといえます。
3. ワクチンを優先的に接種できる
BCPを策定済みの介護事業所に所属する職員は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条にもとづき、感染症拡大時にワクチンを優先接種できます。同法が定める「国民生活・国民経済安定分野の業種に該当する事業者」には介護事業者が含まれており、特定接種の対象となるからです。早期のワクチン接種は施設内での感染拡大を抑制する上で重要な取り組みといえます。このように、利用者・職員の双方が安心して過ごせる環境を維持できる点が大きなメリットです。
4. 税制優遇や補助金/助成金の対象となる
BCPを策定済みの事業者が国の認定を受けることにより、税制優遇や補助金/助成金の対象となる点もメリットの1つです。中小企業防災・減災投資促進税制にもとづく優遇を受けられるほか、自治体の補助金/助成金といった制度を利用できる場合もあります。税制優遇の具体的な条件は次のとおりです。
令和9年3月31日までの間に事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、計画に記載された対象設備の取得等を行い事業に使用した場合に、特別償却16%の税制措置を受けることができます。
※出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置)について」 https://kyoujinnka.smrj.go.jp/guidance/tax_system.html
5. 平時からリスクの抑制/回避につながる
BCPが効果を発揮するのは有事の時だけではありません。平時からBCPにもとづいて訓練を実施したり、緊急事態に直面した際の行動を共有したりする中で、職員の防災意識が高まる効果が期待できます。安全に配慮された施設運営を実現するには、職員の意識向上が不可欠です。BCPの存在を周知し、施設運営の一環として取り入れていくことによって、平時からリスクの抑制/回避に寄与するでしょう。
BCP策定のポイント

介護事業所におけるBCPは、自然災害を想定した計画と感染症のまん延を想定した計画とをそれぞれ分けて策定しておく必要があります。それぞれ策定時のポイントを確認しておきましょう。
自然災害BCP
自然災害BCP策定のポイントは次の4点です。
- 情報を収集・共有するための体制構築
- 平時の対策と被災後の対策に分けて検討
- 優先度の高い業務の見極め
- 計画の周知や研修・訓練の実施
※出典:厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf
情報を収集・共有するための体制構築
平時および災害発生時の情報収集および共有体制、情報伝達のフローを構築しましょう。具体的には、全体の意思決定者、各業務の担当者を明確にするほか、関係者の連絡先や連絡フローをあらかじめ整理しておくことが大切です。
平時の対策と被災後の対策に分けて検討
設備や機器などの耐震固定をはじめ、インフラ(電気・水道等)が機能しなくなった場合を想定して、緊急用のバックアップ電源や給水設備を準備しておく必要があります。また、被災した際に人命および安全を守るために必要とされるルールや、事業の復旧に備えるためのルールを策定し、周知しておくことが重要です。初動対応の際に誰がどう行動するのかを具体的に定め、利用者・職員の安全確保と安否確認をスムーズに行えるようにしましょう。
優先度の高い業務の見極め
業務の優先順位を整理し、限られた人員・設備で重要業務を継続できる体制づくりをしておく必要があります。
計画の周知や研修・訓練の実施
常日頃から研修および訓練を実施し、危機発生時の行動を確認しておくことが大切です。また、訓練を通じて表出した課題への対策を検討し、適宜BCPに反映させて改善を図っていきましょう。
【自然災害BCPに役立つ製品例】
なお、災害対策については次の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
▶企業が取り組むべき災害対策とは? 企業防災の基本的な考え方・具体的な進め方について解説
感染症BCP
感染症BCP策定のポイントは次の5点です。
- 施設・事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築
- 感染(疑い)者が発生した場合の対応
- 職員確保
- 業務の優先順位の整理
- 計画の実行に向けた周知と研修・訓練の実施
※出典:厚生労働省老健局「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/content/001073001.pdf
施設・事業所内を含めた関係者との情報共有と役割分担、判断ができる体制の構築
平時および災害発生時の情報収集・共有体制や、情報伝達フローを構築します。全体の意思決定者、各業務の担当者を明確にすることに加え、関係者の連絡先や連絡フローをまとめておくことが大切です。
感染(疑い)者が発生した場合の対応
感染者および感染疑い者が発生した際に、必要な介護サービスを継続できる体制づくりが求められます。平時から緊急事態を想定したシミュレーションを実施し、感染(疑い)者の個室への移動や防護具・消毒液等の確保などを迅速に進められるよう備えておきましょう。
職員確保
感染者とその他の利用者への介護は、交差感染のリスクを避けるためにも別々の職員が対応するのが望ましいでしょう。職員の確保が難しいことが想定されるようなら、関係団体や都道府県等に応援依頼をすることも想定しておく必要があります。
業務の優先順位の整理
職員が感染した場合を想定し、重要業務を優先的に遂行するための体制を整えておきましょう。限られた人員でも重要業務が滞ることのないよう、業務の優先順位を整理しておくことが大切です。
計画の実行に向けた周知と研修・訓練の実施
平時から研修や訓練(シミュレーション)を実施し、危機発生時に迅速に行動できるようBCPの記載事項を周知しましょう。また、訓練を通じて発見された課題への対応策を検討し、BCPに反映させてアップデートを図ることも重要なポイントです。
介護事業所におけるBCP運用上の課題
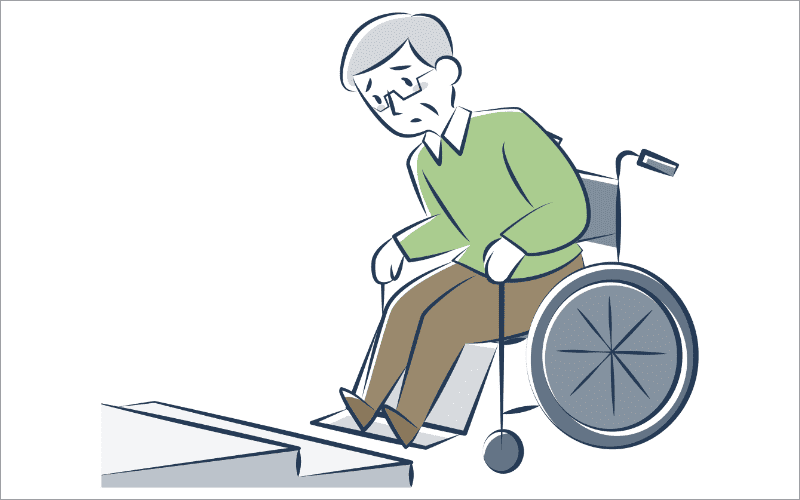
策定したBCPを運用するにあたって、課題として挙がりやすいポイントを紹介します。それぞれの課題への対処方法とあわせて確認しておきましょう。
実効性を検証するための訓練
BCPは策定すること自体が目的ではありません。自然災害や感染症まん延が発生した際、実際に機能する計画にしていくことが重要です。BCPに沿って定期的に訓練を実施し、実効性を検証する必要があるでしょう。
訓練実施に向けた準備を計画的に進めるほか、実施後には必ず総括を行い、抽出された課題をもとにBCPを見直していくことが求められます。こうした取り組みを通じて、有事の際にとるべき行動を現場の職員に理解してもらうことが重要です。
継続的な教育の実施
BCPを効果的に運用できるかどうかは、職員の意識にかかっているといっても過言ではありません。職員向けの研修会や講習会を定期的に実施し、意識向上を図っていく必要があります。年間計画に訓練や研修会・講習会の日程をあらかじめ組み込み、計画的に実施していくことが大切です。研修内容によっては外部専門家を招致するなど、外部人材の活用も積極的に検討しましょう。
介護ニーズへの柔軟な対応
変化し続ける介護ニーズに柔軟に対応していくことも重要な課題の1つです。近年は介護サービスの多様化が進んでいます。それに伴い、介護事業所に求められる機能も細分化していることから、事業所ごとの実態に即したBCP策定がいっそう求められるようになる可能性が高いでしょう。とくに新たなサービスの提供を開始する際にはBCP対策もあわせて検討し、計画を随時更新していく必要があります。
介護事業所のBCPに関するよくある質問
介護事業所のBCPについて、よくある質問をQ&Aにまとめました。疑問点や不明点の解消に役立ててください。
介護事業所のBCPは誰が作成すべきですか?
BCPを策定する部門や担当者について、明確なルールは存在しません。一般的には、危機管理部門やリスクマネジメント部門が中心となって作成するパターンが多く見られます。ただし、介護事業所において該当する部門を設けていないケースも少なくありません。このような場合は、BCPチームを新たに創設して対応するのが現実的でしょう。
BCPにもとづく訓練は年に何回実施する必要がありますか?
BCPにもとづく訓練は入所系の施設で年2回以上、通所系・訪問系の施設で年1回以上の実施が義務づけられています。介護事業所の年間計画に訓練の予定を組み込み、所定の実施回数を遵守できるようにすることが大切です。なお、自然災害・感染症まん延を想定した訓練のいずれも実施する必要があります。
BCP策定は平時/有事ともに役立つ取り組み
BCP策定は介護事業所に義務づけられている取り組みです。BCP未策定の場合、有事の際に適切な対応ができないおそれがあるほか、介護基本報酬の減額対象にもなるため、必ず策定しなければなりません。一方で、BCP策定は有事だけでなく、平時の危機管理意識を高めることにもつながります。より安全で安心できる施設運営を実現するためにも、BCP策定によって得られるメリット面を引き出す取り組みを積極的に推進していくのが得策でしょう。今回紹介したBCP策定のポイントや運用上の課題への対処方法を参考に、BCPの策定・改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
カナデンでは、介護事業所のBCP策定・強化を総合的に支援するソリューションをご提供しています。災害時にも事業を継続するための「リスク分析」から、生命線となる電源・給水を確保する「対策設備の導入」、継続的な「運用支援」まで、ワンストップでお手伝いします。BCP強化でお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。